2025年5月19日に放送された日テレ系「ZIP!」の人気コーナー「山口先生の3分授業」では、「こどもが「読書好き」になるには」という興味深いテーマが特集されました。
子どもにどうやって本を好きになってもらうか、多くの保護者が持つ悩みの一つかもしれません。
この記事では、番組内で山口先生が推薦した、子どもたちの読書への関心を高め、その楽しさや意義を教えてくれる2冊の素晴らしい書籍、『山烋のえほん ゆめわたげ』と『新潮文庫 きみの友だち』について詳しくご紹介します。
それぞれの本が持つ特徴や魅力、そしてどのような点が子どもたちの成長に繋がるのかを具体的に解説していきますので、お子様への一冊を選ぶ際の参考になれば幸いです。
ZIP 山口先生の3分授業「こどもが「読書好き」になるには」
この日の「山口先生の3分授業」では、子どもたちが読書を通じて豊かな心を育み、自ら学ぶ力を伸ばすためのヒントが提供されました。
紹介された2冊は、読書の入口として、また読書の深みを体験するために、それぞれ異なる魅力を持つ作品です。
優しさ繋ぐ絵本『ゆめわたげ』1,980円
『山烋のえほん ゆめわたげ』は、心温まるストーリーと美しい絵で、子どもたちに優しさや共感の気持ちを教えてくれる絵本です。
価格は税込1,980円です。
この絵本の素晴らしい点は、主人公であるウサギくんの行動を通して、自然と利他性や自己肯定感を学べるように構成されていることです。
物語は、春の野原で願いをかなえる“ゆめわたげ”を手にしたウサギくんが、自分のためではなく、友達や家族のためにその願いを使おうと考えるところから展開します。
昔話の「3つの願い」をモチーフにしながらも、現代の子どもたちが共感しやすいテーマが描かれています。
第29回いたばし国際絵本翻訳大賞の英語部門で最優秀翻訳大賞を受賞しており、その質の高さは折り紙付きです。
本文はすべてひらがなで書かれているため、読み聞かせであれば5歳頃から、自分で読むのであれば小学校低学年から楽しむことができます。
ページをめくるたびに引き込まれる美しいイラストは、視線誘導を意識して描かれており、子どもたちの想像力を豊かにします。
また、あえて吹き出しを使わず余白を広く取ることで、読者が自由に物語の世界を想像できるような工夫も凝らされています。
読者からは「友だちの願いを自分の願いにできる優しさが心に響きました」「返礼のラストシーンでは大人も涙してしまいます」といった感動の声が多く寄せられています。
感情教育の導入教材として、また、親子で対話をしながら読み進めることで子どもの自己表現を促す一冊としても最適です。
本当の友達とは?『きみの友だち』880円
重松清さんによる『新潮文庫 きみの友だち』は、思春期を迎える子どもたちが直面する人間関係の複雑さや、「本当の友だちとは何か」という普遍的な問いに深く迫る連作長編小説です。
価格は税込880円と手に取りやすい設定です。
この作品が多くの読者の心を掴む理由は、登場人物たちが抱える“生きづらさ”や葛藤を多角的な視点から丁寧に描いている点にあります。
足に障害を持つ恵美、病気がちな由香、クラスの人気者であるブンちゃん、そして優等生の転校生モトくんなど、それぞれ異なる個性と悩みを抱えた少年少女たちが織りなす物語は、読者に深い共感を呼び起こします。
各話の冒頭に置かれた「さあ、次はきみの話だ」という一文が、読者を物語の当事者として引き込む効果的な仕掛けとなっています。
全8話から成るこの小説は、約320ページと児童文学から一般文芸へのステップアップを目指す中学生にとって、初めて挑戦する長編文庫としても適しています。
部活動、障害、友人関係における嫉妬や誤解、そして和解といった、学校生活で起こりうる様々なテーマが取り上げられており、自分のこととして考えやすい内容です。
2022年度には全国学校図書館協議会の中学推薦図書に選ばれ、2024年度の神奈川県公立高校入試問題で一部が出題されるなど、教育的な価値も高く評価されています。
「読み終えた後、涙が止まらなかった」「友達との関係性について改めて考えさせられた」といった感想が数多く寄せられており、読者の心に強い印象を残す作品です。
多感な時期の子どもたちが自己肯定感を育み、自分の居場所を見つけるための一助となるでしょう。
まとめ:読書で育む、子どもの豊かな心について
今回ご紹介した『山烋のえほん ゆめわたげ』と『新潮文庫 きみの友だち』は、子どもたちが読書の楽しさに目覚め、物語を通じて多くのことを学ぶ素晴らしい機会を提供してくれます。
絵本で育まれる優しい心、小説を通じて深まる他者への理解は、子どもたちの人生をより豊かにしてくれることでしょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
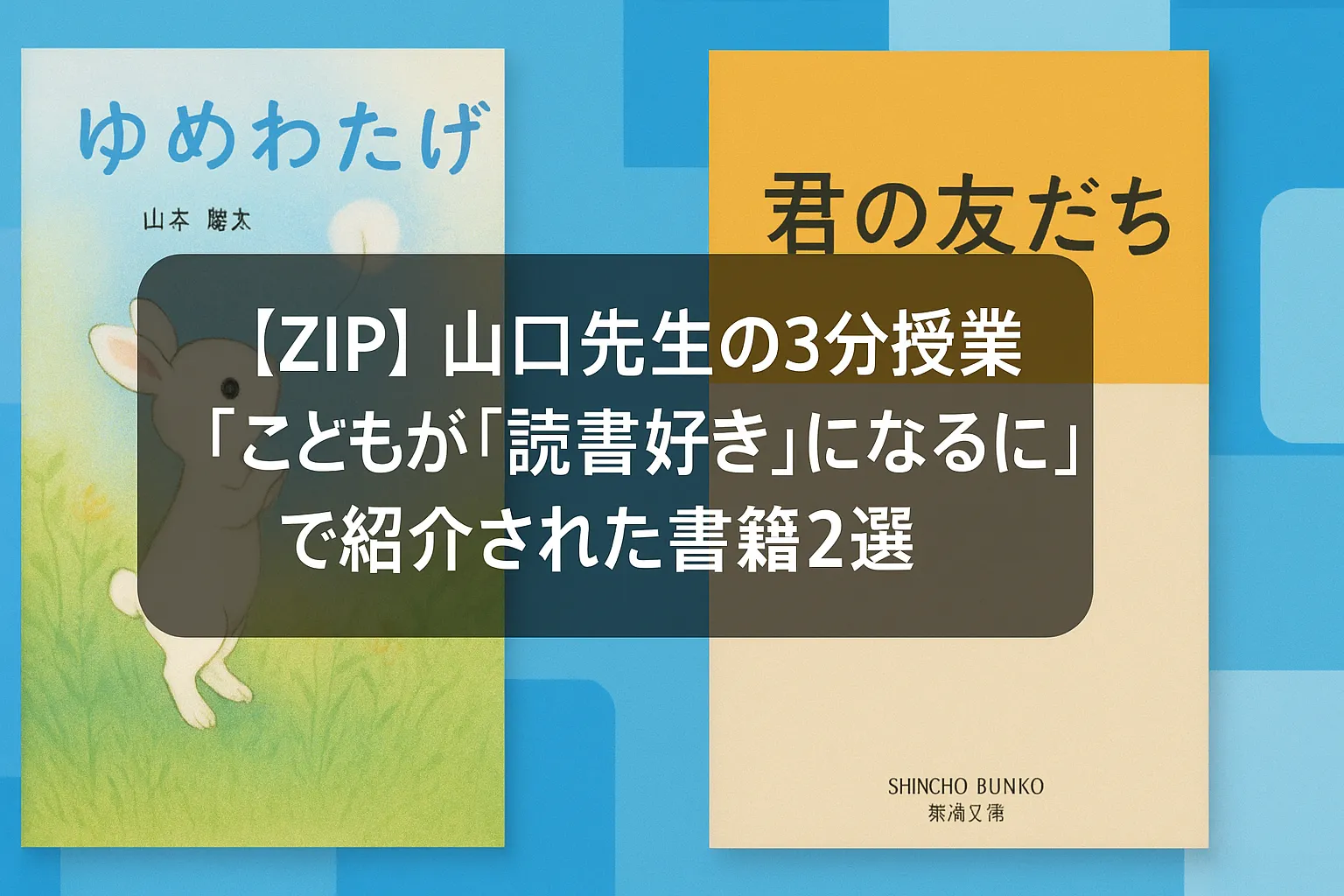








コメント