2025年5月11日に放送されたテレビ朝日系『相葉マナブ』の人気コーナー、「マナブ!初めまして食材~ザーサイ~」では、普段あまり馴染みのない「生」のザーサイにスポットライトが当てられました。
この記事では、同番組で紹介された数々のザーサイ料理の中から、特に家庭で手軽に作れる「ザーサイのナムル」のレシピを詳しくご紹介します。
「生」のザーサイとはどんな食材なのか、その特徴から、具体的な材料、調理手順、さらにはプロが教える美味しく仕上げるためのコツや、番組内で提案された簡単アレンジアイデアまで、余すところなく解説していきます。
この記事を読めば、あなたもきっと「ザーサイのナムル」を作りたくなるはずです。
シャキシャキとした食感と豊かな風味をご家庭でぜひお楽しみください。
相葉マナブ #590 マナブ!初めまして食材~ザーサイ~
2025年5月11日の放送回、#590では「マナブ!初めまして食材~ザーサイ~」として、千葉県館山市のザーサイ農家を訪問しました。
出演者の相葉雅紀さん、小峠英二さん(バイきんぐ)、岡部大さん(ハナコ)が、収穫されたばかりの新鮮な生のザーサイを使い、その美味しさを引き出す4品のレシピを学びました。
一般的には加工された状態で見ることが多いザーサイですが、番組では「生」ならではの食感と旨味に注目しました。
ザーサイのナムル 紹介
今回ご紹介する「ザーサイのナムル」は、番組で紹介された4品の中でも、特に生のザーサイの魅力をダイレクトに味わえる一品です。
火を使わずに数分で完成する手軽さながら、その風味と食感は本格的です。
ザクッとした歯ごたえと、香味野菜やゴマ油が織りなすコク深い味わいが楽しめます。
シャキシャキ食感!あの絶品和え物の材料
この「ザーサイのナムル」を作るために必要な材料は、ご家庭にも常備されていることが多い、わずか5種類です。
主役となる生のザーサイは100g準備します。
生のザーサイは、塩蔵品に比べてビタミンCや葉酸の残存率が高いという特徴があります。
また、食物繊維やカリウムも豊富に含んでいます。
- ザーサイ 100g
- 塩 小さじ1
- おろしにんにく 小さじ1/2
- 白いりゴマ 小さじ1
- ゴマ油 小さじ1
これらの分量で、2~3人分のナムルが出来上がります。
おろしにんにくのピリッとした辛味と香り、白いりゴマの香ばしさ、そしてゴマ油の豊かな風味が、ザーサイの味を一層引き立てます。
驚くほど簡単!あっという間の作り方
調理工程は非常にシンプルで、誰でも簡単に美味しいナムルを作ることができます。
わずか2つのステップで、あっという間に副菜が一品完成します。
最も重要なポイントは、ザーサイから出る水分をしっかりと取り除くことです。
これにより、味が薄まらず、食感も良く仕上がります。
- 下準備 : ザーサイはまず細切りにします。
ボウルに移し、塩(小さじ1)を振って手でよく揉み込みます。
ザーサイから水分が出てきたら、一度水で洗い流します。
その後、手でギュッと絞り、さらにキッチンペーパーを使って念入りに水気を拭き取ります。
この塩揉みと水洗いの工程によって、ザーサイの余分な塩分やアクが抜け、旨味が凝縮されるとともに、独特の良い食感が生まれます。 - 和える : 別の清潔な器を用意し、そこにおろしにんにく(小さじ1/2)、ゴマ油(小さじ1)、そして白いりゴマ(小さじ1)を入れてよく混ぜ合わせます。
この合わせ調味料の中に、下準備を終えたザーサイを加え、全体が均一になるように丁寧に和えれば、美味しい「ザーサイのナムル」の完成です。
ゴマ油の豊かな香りとニンニクの食欲をそそる風味が、ザーサイ本来の持つピリッとした辛味を程よくマイルドに調和させます。
仕上げに加える白いりゴマは、香ばしさをプラスするだけでなく、見た目にも美しいアクセントとなります。
番組のスタジオでは、このナムルをシンプルにそのまま味わう以外にも、「冷奴の上にのせる」「納豆と一緒に混ぜ合わせる」といった、手軽で美味しいアレンジ方法が提案され、その応用の幅広さも魅力として伝えられました。
千葉県館山市は、その温暖な気候と霜が降りにくいという特性から、ザーサイ栽培に適した土地柄です。
現地の農家では、種まきからおよそ90日という短い期間で、直径が15cmを超えるほど立派なザーサイの根塊を収穫しています。
「鮮度の良い生のザーサイだからこそ、漬物だけに頼らない多様な調理法でその真価を発揮できる」と、番組では紹介されていました。
この「ザーサイのナムル」は、そんな新鮮な生ザーサイの魅力を、日本の家庭料理にも取り入れやすい形で提案した、まさに決定版ともいえるレシピです。
相葉マナブ式ザーサイナムルの魅力について
今回は、『相葉マナブ』で紹介された「ザーサイのナムル」のレシピを中心に、生のザーサイの魅力や調理のポイントをお届けしました。
非常に簡単な手順で、素材本来の味を活かした美味しい一品が楽しめますので、ぜひご家庭で試してみてください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
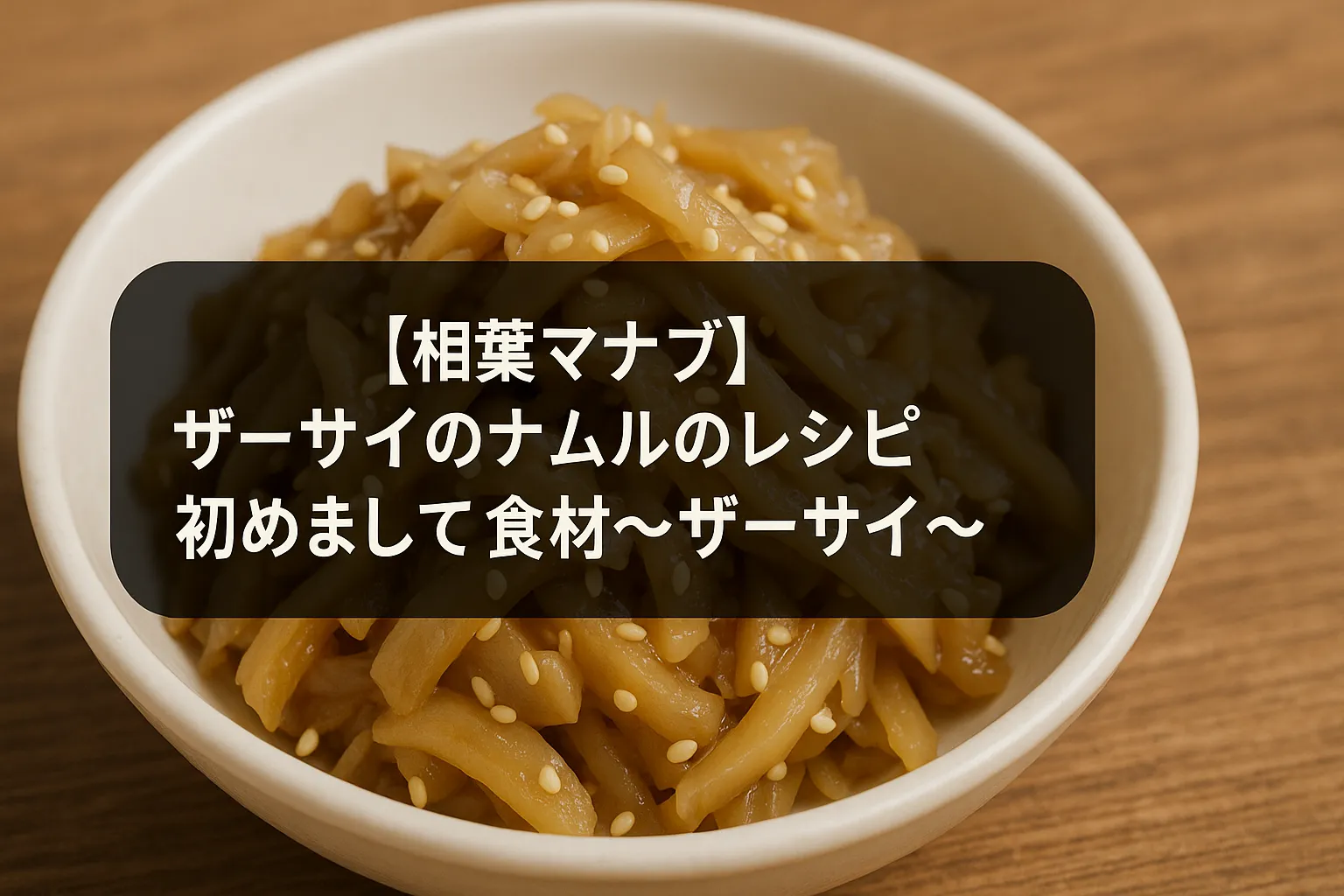








コメント