2025年5月14日にNHKで放送された「クローズアップ現代」では、「弁護士にだまされる?追跡!“着手金トラブル”」と題し、全国で急増している弁護士による着手金トラブルの深刻な実態が取り上げられました。
この記事を読めば、番組で明らかにされた被害の現状、悪質な弁護士の手口、そして私たち消費者がどのようにして身を守ればよいのか、具体的な対策に至るまで詳しく理解することができます。
詐欺被害に遭い、最後の望みを託した弁護士からさらなる被害を受ける「二次被害」の構造や、その背景にある問題点、そして専門家からのアドバイスまで、番組で取り上げられた重要な情報を網羅的に解説します。
クローズアップ現代
2025年5月14日(水)19:30から放送されたNHKの報道番組「クローズアップ現代」は、近年深刻化している弁護士による着手金トラブルの問題に焦点を当てました。
キャスターの桑子真帆さん、東京弁護士会 非弁提携弁護士対策本部の小早川真行弁護士、そして実際に被害に遭われた出原誠太郎さんが出演し、被害の現状と背景にある構造的な問題について議論が交わされました。
追跡!弁護士着手金トラブル衝撃の実態
弁護士に相談したにもかかわらず、かえって被害が拡大してしまう「着手金トラブル」が全国で後を絶ちません。
番組では、詐欺被害の回復を謳い高額な着手金を受け取りながら、実際にはほとんど業務を行わず依頼者を放置する悪質な事例が複数紹介されました。
驚くべきことに、NHKが独自に行った調査によると、過去4年間で全国11人の弁護士が懲戒請求や弁護士法違反の罪で問題視され、これらの弁護士によって巻き込まれた被害者は少なくとも8000人以上、着手金の総額は50億円を超えるという衝撃的な実態が明らかになりました。
被害者の多くは、既に何らかの詐欺被害に遭っており、その救済を求めて弁護士に依頼した結果、進捗の連絡もないまま放置され、「二重の被害」に苦しむという深刻な事態に陥っています。
なぜ?弁護士Bが語る転落の経緯と手口
番組では、実際に懲戒処分を受け、弁護士法違反の罪で起訴された弁護士B氏(仮名)本人の証言が放送されました。
B氏が詐欺被害金の回収業務をうたい始めたのは4年前、知人から「ネット広告を出して依頼を多く集めれば安定収入になる」と持ちかけられたことがきっかけでした。
当時、インターネット広告に関する知識や経験が乏しかったB氏は、紹介された広告会社に広告の作成から運用まで全面的に委託し、自身は最初の契約段階にのみ関与するという形を取りました。
その結果、広告会社が作成した広告には、実際には対応できない「24時間365日対応」といった表示や、B氏本人とは異なる見栄えの良い人物の写真が無断で使用されたり、「詐欺被害に強い弁護士が返金請求」といった、B氏の実績とはかけ離れた専門性を誇張する表現が用いられたりしました。
これらの虚偽・誇大な広告によって、わずか8ヶ月の間に全国から270人以上もの相談が殺到し、契約に至りました。
着手金の総額は1億円にも達しましたが、B氏にはこれほど大量の案件を適切に処理できる体制も経験もありませんでした。
結果として、多くの案件が放置され、依頼者への説明もなされないまま被害が拡大したのです。
さらに、集められた1億円もの着手金の大半は、広告会社への広告費や関連する事務処理手数料といった名目で支払われ、B氏自身の手元にはごく一部の金額しか残らなかったとされています。
この事例は、弁護士自身が業務の実態を十分に把握せず、外部の業者に安易に依存することの危険性と、誇大広告がもたらす深刻な結果を如実に示しています。
B氏はその責任を問われ、最終的に弁護士法違反で逮捕・起訴されました。
見えにくい罠!「非弁屋」と広告の危険な関係
弁護士B氏の事例で明らかになったように、着手金トラブルの背景には、しばしば悪質な広告会社や、弁護士資格を持たないにもかかわらず報酬目的で法律事務に関与する「非弁屋」の存在があります。
「非弁屋」とは、弁護士資格を持たない者が、報酬を得る目的で法律事務を取り扱ったり、弁護士に事件を斡旋したりする者を指し、その活動は弁護士法第72条に明確に違反します。
彼らは、集客に悩む弁護士などに広告業者を装って接近し、名義貸しを強要したり、事務所に従業員を送り込んで業務を乗っ取ったり、不当な報酬分配を行ったりするのです。
また、悪質な広告会社は、弁護士の集客支援を名目に、実際には虚偽や誇大な内容を含む広告を積極的に展開します。
「24時間365日対応」と謳いながら実態がなかったり、弁護士本人の写真ではなく無関係なモデルの写真を使用したり、「〇〇分野の専門家」「勝率〇割」といった根拠のない実績をアピールしたりするのです。
これらの広告は、日本弁護士連合会が定める「弁護士等の業務広告に関する規程」や景品表示法に抵触する可能性が極めて高い行為です。
さらに、インターネット広告の分野では、SEO技術を悪用した「SEOスパム」(コンテンツの無断複製、隠しテキスト、不自然なキーワードの多用など)や、口コミサイト・SNSでの評価を不正に操作する「やらせ口コミ」「ステルスマーケティング」といった手口も用いられ、消費者を誤認させ不利益な契約へと誘導する危険性があります。
こうした「経済的困難や集客に悩む弁護士」、「過度な成果を約束し高額な広告費を請求する広告会社」、そして「弁護士の名義を利用して実質的に法律業務を支配し利益を得ようとする非弁屋」という三者の利害が複雑に絡み合い、相互に依存することで、一種の「負のエコシステム」が形成されているのです。
もう騙されない!悪質弁護士から身を守る知恵
弁護士という肩書きが必ずしも信頼の証ではないという厳しい現実が、今回の放送で浮き彫りになりました。
資格があるというだけで相手を信用してしまうのは非常に危険です。
高額な着手金を支払ったにもかかわらず、十分な対応をされないまま終わるケースが多数確認されています。
番組では、このような被害を未然に防ぎ、信頼できる弁護士を見極めるための具体的なポイントも紹介されました。
まず最も重要なのは、契約前に弁護士本人と必ず面談することです。
書類や電話だけのやり取りではなく、直接会って説明を受けることが信頼性を確かめる第一歩となります。
次に、業務内容と費用の内訳が明記された委任契約書を必ず作成してもらい、その内容を隅々まで十分に確認することが不可欠です。
契約書には、具体的にどのような事件処理を依頼するのか、その範囲、着手金・報酬金の金額と算定根拠、支払時期、実費の種類と概算額、事件処理の見通しや報告義務、契約解除に関する条項などが明確に記載されているかを確認しましょう。
「成功報酬制」や「無料相談」といった魅力的に見える言葉にも注意が必要です。
実際には別の名目で費用が発生する場合がありますので、言葉の印象だけで判断せず、内容をしっかり確認することが求められます。
また、インターネット上の広告や口コミサイトの情報だけを鵜呑みにせず、実際にその弁護士が所属している弁護士会のウェブサイトなどで登録情報を調べて確認することも有効な手段です。
具体的に悪質な弁護士広告を見分けるポイントとしては、「過度に安い料金や『無料相談』の強調」、「『〇〇専門』『必ず解決』といった専門性や実績の誇張」、「所属弁護士会や弁護士名の不明確な表示」、「過度に不安を煽る表現」、「公的機関との関連を誤認させる表示」などが挙げられます。
少しでも疑問や不安を感じたら、契約を急がず、地域の弁護士会や消費生活センターに相談することも検討しましょう。
第三者の視点から情報を得ることで、冷静な判断がしやすくなります。
依頼者自身がしっかりと情報を見極め、自分を守るための知識を持つことが何よりも大切ですです。
まとめ:弁護士着手金トラブルから身を守るために必要なことについて
NHK「クローズアップ現代」で取り上げられた弁護士による着手金トラブルは、被害者にとって経済的にも精神的にも大きな打撃を与える深刻な問題です。
悪質な手口は巧妙化しており、弁護士という専門家を安易に信頼してしまうと、思わぬ二次被害に遭う危険性があります。
この記事で紹介したトラブルの実態、悪質な業者の手口、そして具体的な自衛策を参考に、万が一の際に冷静に対応できるよう備えておくことが重要です。
契約前の面談や契約書の確認、そして第三者機関への相談をためらわない姿勢が、自身を守るための鍵となります。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
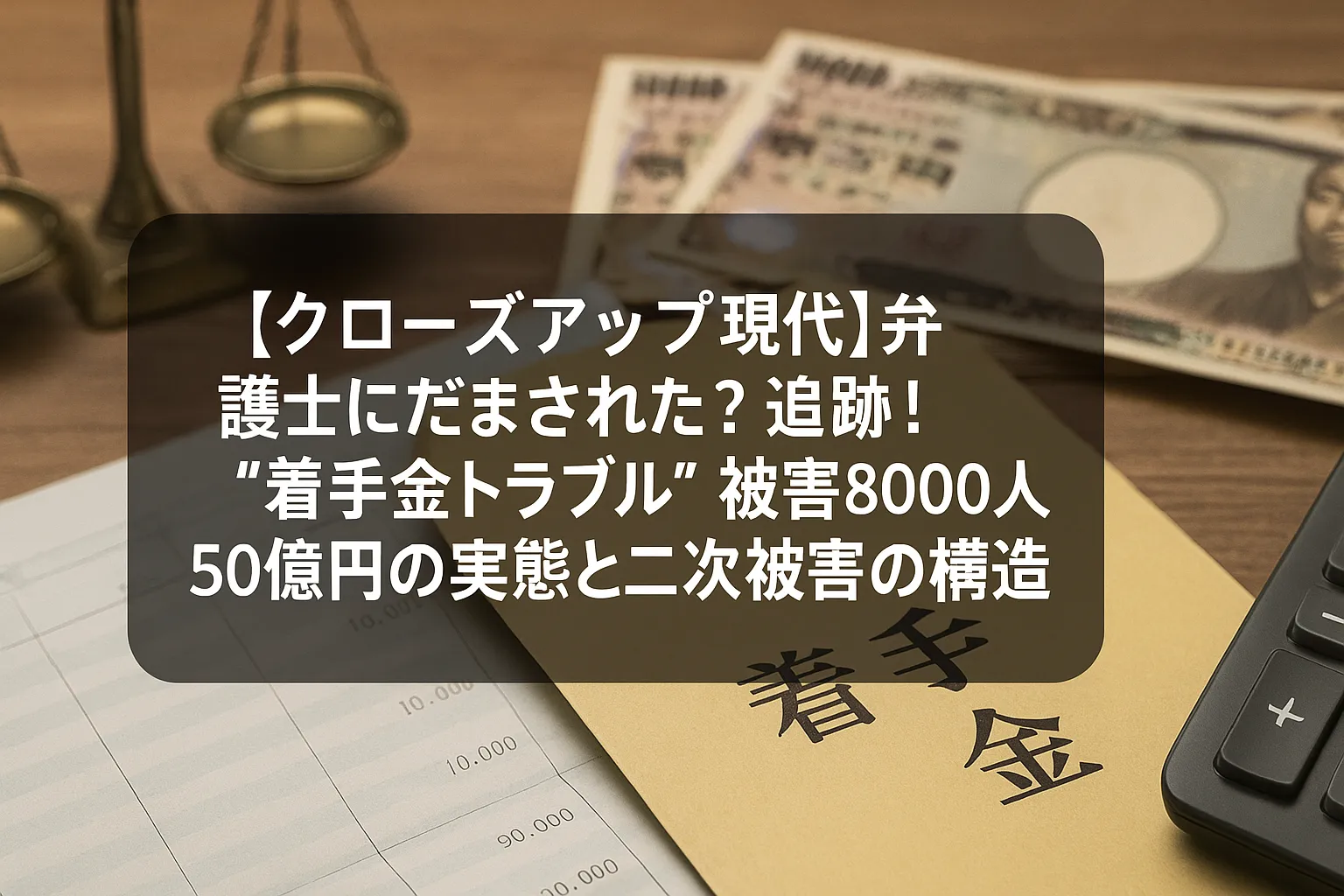



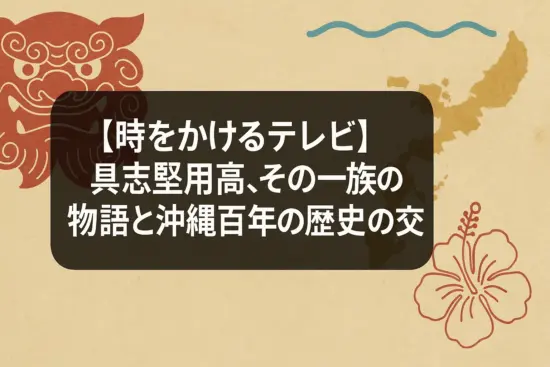
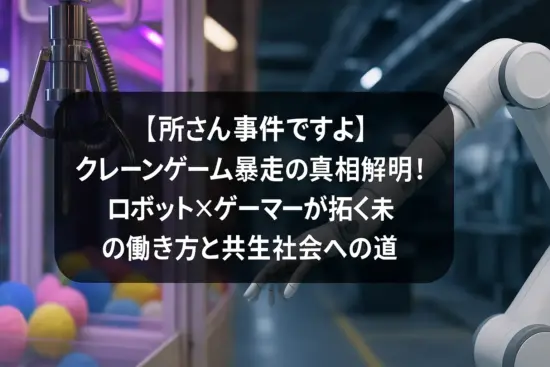

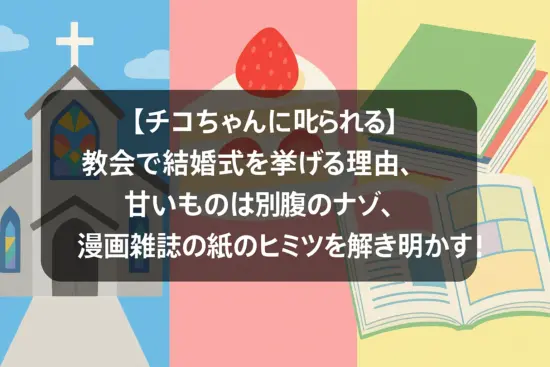

コメント