2025年5月16日にNHK総合で放送された『時をかけるテレビ』では、「具志堅用高とその一族の100年史と沖縄の歩み」と題し、1979年のNHK特集「わが沖縄〜具志堅用高とその一族〜」を振り返りました。
この記事を読めば、沖縄初の世界チャンピオンである具志堅用高さんの輝かしい功績だけでなく、その背景にある琉球王国時代にまで遡る具志堅一族の壮絶な歴史、そして明治時代の「琉球処分」から太平洋戦争、戦後の米軍統治、本土復帰に至る沖縄の激動の100年が、具志堅さんの人生といかに深く結びついているのかが分かります。
さらに、沖縄の伝統文化や家族の絆、そして時代を超えて語り継がれる物語が現代に投げかけるメッセージについても深く理解することができるでしょう。
時をかけるテレビ:具志堅用高と沖縄100年史
2025年5月16日(金)22時30分からNHK総合で放送された『時をかけるテレビ』は、特別な内容でお届けされました。
ジャーナリストの池上彰さんが案内役を務め、今から45年以上前、1979年に放送されたNHK特集「わが沖縄〜具志堅用高とその一族〜」というドキュメンタリー番組を再訪しました。
スタジオには、沖縄県出身者として初めてボクシングの世界チャンピオンに輝いた具志堅用高さんご本人を迎え、ご自身の一族の歩みと沖縄の激動の歴史が重なる映像を改めて見つめ直しました。
琉球士族の末裔、翻弄された一族の誇りとは?
具志堅用高さんのご家族は、かつて琉球王国に仕えた「士族」という身分の家系です。
王国が存在した時代には、役人として誇り高く生活を送っていました。
しかし、その生活は明治12年(1879年)の「琉球処分」によって一変します。
この歴史的な出来事により琉球王国は消滅し、沖縄県として日本に組み込まれたのです。
この大きな変化は、具志堅一族にとっても深刻な影響を及ぼしました。
それまで持っていた士族としての地位や安定した収入を失い、生活の基盤が崩壊してしまいます。
誇りを胸に抱きつつも、多くの一族が沖縄本島の本部町をはじめとする県内各地へ散らばり、慣れない土地で農業や漁業に従事するなど、新たな生活を切り開いていくことを余儀なくされました。
時代は進み、明治31年(1898年)には、沖縄県にも徴兵令が施行されることになります。
具志堅用高さんの祖父にあたる用高(ようこう)さんも、明治44年(1911年)に徴兵されました。
当時の沖縄の若者たちは標準語をほとんど話せなかったため、軍隊内での意思疎通は非常に困難でした。
しかし、用高さんは言葉の壁に臆することなく、得意だった銃剣術で抜群の腕前を発揮し、部隊内で高く評価される存在となったのです。
この、言葉が通じなくても自身の技量で信頼を勝ち取った祖父の姿は、具志堅一族の中で、困難に立ち向かう誇り高い精神の象徴として語り継がれています。
南洋移民、戦争、土地接収…沖縄の試練
昭和の時代に入ると、沖縄の経済状況はさらに厳しいものとなっていきました。
生活の糧を求めて、多くの沖縄県民が日本の委任統治領だった南洋群島(現在のパラオやサイパンなど)へと移住する道を選びます。
具志堅一族の中にも、この南洋移民の波に乗り、漁業に従事する人々が増えました。
当時の南洋での漁師の収入は非常に高く、一時は沖縄県知事の年収を超えるほどの稼ぎを得る人もいたほどです。
稼いだお金は沖縄の家族に送金され、故郷の生活を支えました。
しかし、太平洋戦争が勃発すると、南洋群島での平穏な生活は終わりを告げます。
これらの島々は日米両軍の激しい戦闘の舞台となり、多くの民間人が戦火に巻き込まれました。
具志堅一族も例外ではなく、南洋に移住していた人々のうち、実に4分の1もの人々がサイパン、パラオ、ボルネオといった島々での戦闘や空襲、あるいは飢餓や病によって命を落とすという、あまりにも大きな犠牲を強いられました。
家族との再会も叶わぬまま異郷の地で亡くなった方や、住んでいた島からの避難や強制収容を経験した方も少なくありませんでした。
終戦を迎え、生き残った人々が沖縄へ戻っても、試練は続きました。
具志堅用高さんの一族が3代にわたって暮らしてきた沖縄本島北部の崎原(さきばる)という集落は、戦後、米軍によって飛行場建設のために土地が接収され、廃村となってしまったのです。
先祖代々守り続けてきた土地だけでなく、家も、そして沖縄の人々にとって非常に大切な先祖の墓も移転せざるを得なくなり、一族は心の拠り所である「帰る場所」そのものを失いました。
沖縄の星!具志堅用高、世界への拳と魂
沖縄が27年間のアメリカ統治を経て日本に本土復帰したのは1972年のことです。
そのわずか2年後、1974年に具志堅用高さんは大きな決断をします。
当時、高校ボクシングでオリンピック候補としても注目されていましたが、「金メダルよりカネ」という現実的な目標を掲げ、プロボクサーの道を選び沖縄から上京しました。
この言葉の背景には、当時の沖縄の厳しい経済事情と、家族を支えたいという強い思いがあったのです。
東京の協栄ボクシングジムに所属した具志堅さんは、厳しいトレーニングに励み、驚異的なスピードで才能を開花させます。
そして1976年10月、デビューからわずか9戦目でWBA世界ジュニアフライ級(現在のライトフライ級)王座に挑戦し、見事KO勝利。
沖縄県出身者として初めての世界チャンピオン誕生という歴史的快挙を成し遂げ、沖縄全体が歓喜に沸きました。
その後、具志堅さんは破竹の勢いで防衛を重ね、4年半の間に世界戦13回連続防衛という、当時の日本記録を打ち立てます。
リングに立つとき、彼はいつも「自分は沖縄を背負っている」という強い意識を胸に抱いていました。
インタビューやテレビ出演の際には一貫して沖縄の方言を使い続け、故郷への誇りを示し続けたのです。
世界チャンピオンとして沖縄に凱旋した際には、空港や沿道に多くの県民が詰めかけ、熱狂的な歓迎を受けました。
1979年7月29日、福岡県小倉市で行われた9度目の世界タイトル防衛戦は、具志堅さんと一族にとって特別な一日でした。
対戦相手は強豪ラファエル・ペドロサ選手。
この日、沖縄本島、石垣島、名護市、そして横浜や大阪、岐阜などに暮らす具志堅一族は、それぞれの場所でテレビの前に集い、固唾をのんで試合を見守りました。
試合は判定の末、具志堅さんが見事防衛に成功。
KO勝ちとはならなかったものの、一族の絆を再確認する一戦となりました。
さらにこの年は、具志堅さんと同じ「用高」という名前を持つ親族の一人が米寿(88歳)を迎える年でもありました。
この親族の用高さんは、明治時代に沖縄に入植し、琉球処分後の混乱、戦争、戦後の土地喪失と再出発という、まさに沖縄の激動の歴史そのものを生き抜いてきた人物です。
具志堅さんはこの年長者に対し、「自分はこの人たちの背中を見て育ってきた。尊敬している」と語り、先人への深い感謝と敬意が、リングに立つ力の源となっていることを示しました。
家族の祈り、高円寺の沖縄料理店の温もり
具志堅用高さんの偉業の背景には、家族の力強い支えがありました。
母のツネさんは沖縄・久高島の出身で、父の用敬さんは若い頃に岐阜県の工場で働いた後、沖縄へ戻りカツオ漁師として家族を養いました。
二人は出稼ぎ先で出会い、厳しい時代を共に生き抜き、息子を支え続けました。
具志堅さんが世界チャンピオンとなり、地元・石垣島に新築の家を建てることができたのは、まさに家族の努力と愛情の結晶でした。
また、具志堅さんの大切な試合の日が、沖縄の伝統行事である「清明祭(シーミー)」と重なることもありました。
清明祭は、先祖を敬い、一族が墓前に集まって供養を行う沖縄にとって非常に重要な日です。
試合当日、具志堅一族は先祖代々の墓の前に集まり、海の向こうで戦う彼の勝利を心から祈っていました。
その姿は、スポーツという枠を超えた、家族の深い精神的な絆と、地域全体が具志堅さんに託した願いを象徴していました。
そして、具志堅さんにとって東京でのもうひとつの“ふるさと”と呼べる場所がありました。
それは、東京・高円寺にあった一軒の沖縄料理店です。
石垣島出身の初代店主が営んでいたこの店は、具志堅さんがまだ世界チャンピオンになる前から通っていた思い出の場所でした。
具志堅さんの試合がテレビ中継される日には、この店が沖縄出身者たちの“応援の場”となり、狭い店内は試合開始前から多くの人々で溢れかえり、まるで沖縄の集落のような熱気に包まれたといいます。
勝利のたびに島唄が響き、泡盛で祝杯が交わされる光景は、具志堅さんにとって大きな力となったことでしょう。
現在は、東京出身の2代目店主がその味と空間、そして沖縄の心を引き継ぎ、沖縄文化を伝える活動にも取り組んでいます。
時を超え響く、沖縄100年の物語の今
具志堅用高さんのボクサーとしての活躍は、単に個人の栄光に留まるものではありませんでした。
それは、琉球王国時代から続く一族の誇り、そして戦争や占領、復帰という激動の歴史を生き抜いてきた沖縄の人々の記憶と希望を一身に背負った戦いでした。
だからこそ、彼の勝利は多くの人々の心を震わせ、沖縄全体に勇気と誇りを与えたのです。
1979年に放送されたNHK特集「わが沖縄〜具志堅用高とその一族〜」は、そのような具志堅さんと沖縄の物語を記録した貴重なドキュメンタリーです。
そして2025年、この番組が『時をかけるテレビ』という形で45年以上の時を経て再び光を当てられたことは、非常に大きな意味を持っています。
それは、沖縄が経験してきた苦難の歴史や、今なお抱える基地問題、歴史認識といった課題が、決して過去のものではなく、現代社会に生きる私たちにとっても重要な問いであり続けていることを示唆しています。
番組では、具志堅用高さん本人がスタジオで過去の映像と向き合い、当時の心境や現代への思いを語りました。
個人の記憶と、ドキュメンタリーという公的な記録が交差することで、歴史の多層性や時間の重みがより深く感じられます。
テレビというメディアが、単に情報を伝えるだけでなく、歴史的な記憶を記録・保存し、時代ごとの視点から再解釈し、そして世代を超えて継承していく力を持っていることを、改めて教えてくれました。
具志堅用高さんと彼の一族の物語は、沖縄の100年を映し出す鏡であり、その輝きと痛みは、これからも多くの人々の心に響き続けることでしょう。
まとめ:具志堅用高と沖縄100年の物語について
具志堅用高さんとその一族の100年にわたる物語は、琉球処分から戦争、そして現代に至る沖縄の激動の歴史そのものを色濃く反映しています。
番組『時をかけるテレビ』を通じて、私たちは個人の偉業の裏にある家族の絆、故郷への想い、そして時代を超えて受け継がれるべき沖縄の精神に触れることができました。
この物語は、私たちに多くのことを問いかけ、未来への希望を与えてくれます。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
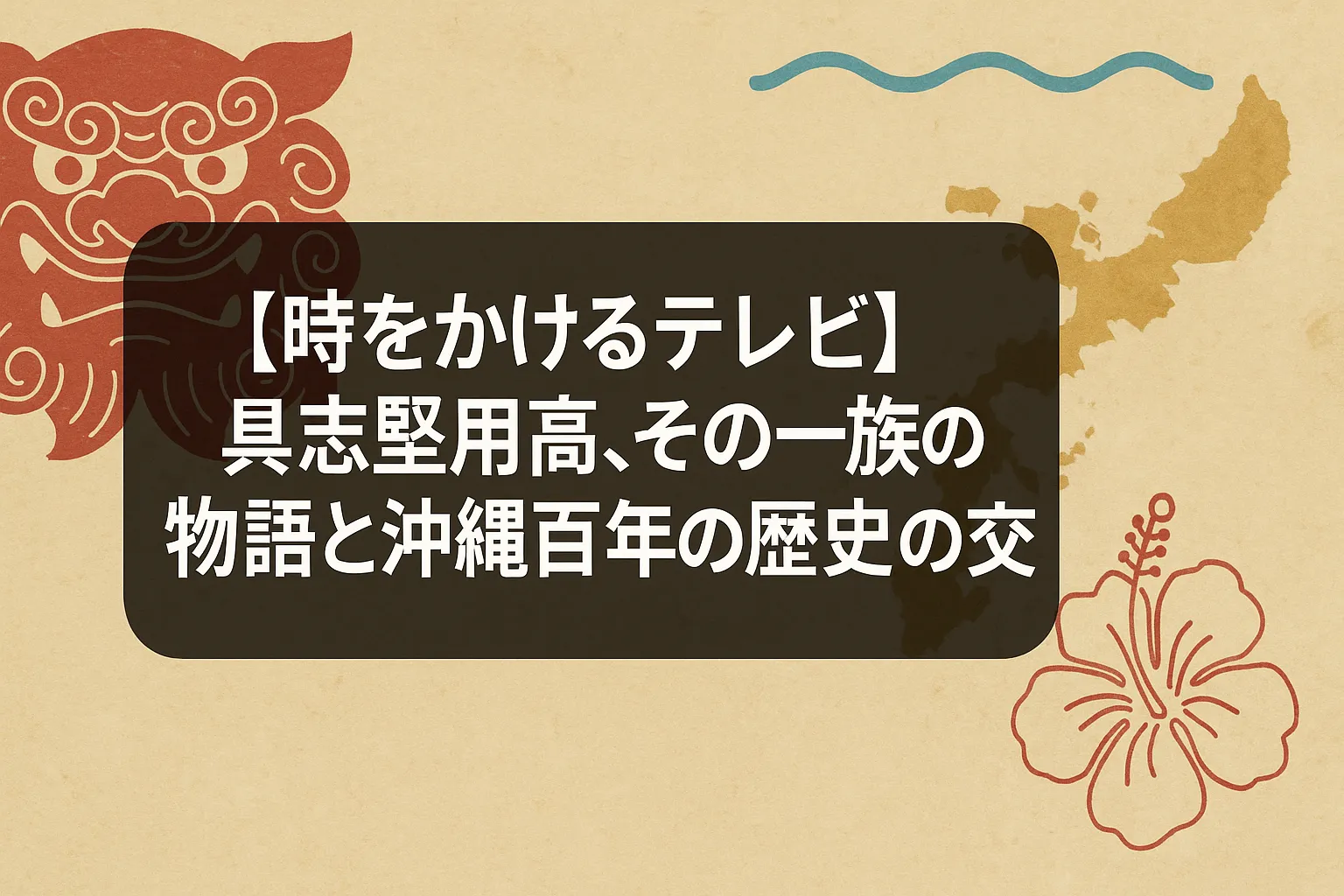



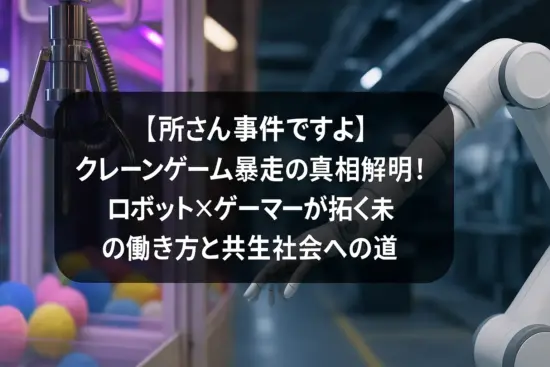

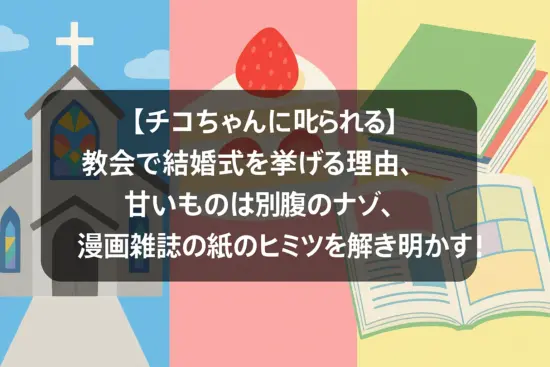

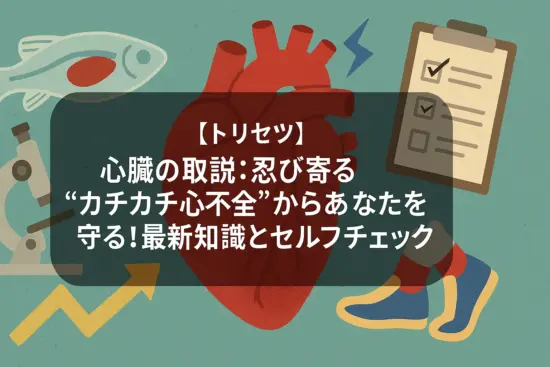
コメント