2025年5月11日放送のNHK総合「うまいッ!」では、高知県安芸市で育まれる特産地鶏「土佐ジロー」の魅力に光を当てます。
「あふれ出すうまみ」をテーマに、その生産の現場と、なぜ多くの人々を虜にするのか、その秘密を深く掘り下げていきます。
この記事を読めば、土佐ジローが持つ鶏本来の野趣あふれる味わいや、生産者である小松靖一さんご夫妻の品質にかける熱い想い、そして「鶏を鶏らしく育てる」という哲学に基づいたユニークな飼育方法が分かります。
さらに、土佐ジローが過疎化に直面する地域にもたらす希望や、東京の料理人をも唸らせる絶品料理の数々まで、土佐ジローの奥深い世界を余すところなくお伝えします。
うまいッ!高知の極上地鶏土佐ジローSP
NHK総合テレビの人気番組「うまいッ!」が、2025年5月11日の放送で高知県の誇る特産地鶏「土佐ジロー」を特集します。
食材ハンターの板橋駿谷さんが現地を訪れ、その生産の背景や味わいの秘密に迫る内容です。
鶏の原点?土佐ジロー驚きの秘密とは
土佐ジローは、まさに鶏の原点に近い魅力を持つ地鶏です。
その誕生の背景には、高知県の熱意と緻密な計画がありました。
この鶏は、高知県原産の天然記念物である「土佐地鶏」の雄と、アメリカ原産の卵肉兼用種「ロードアイランドレッド」の雌を交配して生まれる一代雑種(F1)です。
一代雑種とは、異なる品種の親から一代限りの子孫を作ることで、両親の優れた形質を受け継ぎやすいという特徴があります。
このため、土佐ジロー同士を交配して生まれた鶏(F2世代)は、厳密には「土佐ジロー」とは認定されません。
この一代限りの生産方法が、常に高い品質を保つ秘訣の一つなのです。
開発は昭和54年(1979年)に高知県畜産試験場で始まり、昭和62年(1987年)には本格的なヒナの生産が開始されました。
「土佐ジロー」という名前は、父鶏の土佐「地」鶏の「ジ」と、母鶏である「ロー」ドアイランドレッドの「ロー」を組み合わせて名付けられました。
土佐ジローの肉質は、脂肪分が少なく、赤みが強いのが大きな特徴。
適度な歯ごたえがあり、噛みしめるほどに野趣あふれる濃厚なうま味が口の中に広がります。
一般的なブロイラーが約45日から60日で出荷されるのに対し、土佐ジローは雄で約150日、雌に至っては約450日という長い期間をかけてじっくりと育てられます。
この長期飼育が、筋肉質で引き締まった、ジビエにも例えられるほどの独特な肉質を形成するのです。
うま味成分であるアミノ酸、特にグルタミン酸がモモ肉に多く含まれていることも、その濃厚な風味に寄与しています。
卵もまた格別です。
1個あたり約40g前後と小ぶりで、市販のSSサイズからSサイズに相当しますが、重量に対して卵黄の占める割合が非常に大きいのが特徴。
緑餌を多く与えるため、卵黄の色は鮮やかで濃い黄色を呈します。
卵黄も卵白も盛り上がりが良く、濃厚でコクのある味わいは、甘みすら感じられると評されるほど。
飼育は雌雄同居が基本であるため、生産される卵は有精卵となります。
栄養価も高く、特にビタミンEやカロテンの含有量が多い傾向にあります。
畑山にかける情熱!小松さんの挑戦物語
高知県安芸市の山あい、畑山地区。
ここで土佐ジローの生産に情熱を注ぐのが、小松靖一さんご夫妻です。
小松さんの土佐ジローへの取り組みは、単なる養鶏の域を超えた、品質への飽くなき探求と地域への深い愛情に貫かれています。
小松さんは元々、土佐ジローの卵の生産を手がけていましたが、より高い付加価値を追求するため、肉用としての鶏の育成にも挑戦を開始しました。
しかし、その道のりは平坦ではありませんでした。
理想とする肉質に到達するまでには、実に10年以上もの歳月をかけた試行錯誤があったといいます。
土佐ジローは体が小柄なため、肉用として飼育を始めた当初は可食部の歩留まりが悪く、採算性の面で大きな課題に直面しました。
それでも小松さんは諦めず、「鶏を鶏らしく育てる」という一貫した哲学のもと、研究と改良を重ね、独自の飼育法を確立するに至りました。
そのこだわりは飼育方法だけでなく、提供方法にも及びます。
特に土佐ジローの炭火焼きについては、焼き方を誤ると本来の美味しさが損なわれるとして、自ら焼き方を指導したり、顧客に提供する際には自ら焼いたりするなど、火入れの技術に強いこだわりを持っています。
妻である圭子さんは元新聞記者で、その経験を活かし、靖一さんと二人三脚で土佐ジローのブランド価値向上と、過疎化が進む畑山地区の地域活性化に情熱を注いでいます。
これが秘訣?鶏舎と愛情たっぷり飼育法
小松靖一さんが実践する土佐ジローの飼育法には、その美味しさを引き出すための数々の工夫と、鶏への深い愛情が込められています。
「鶏を鶏らしく育てる」という哲学が、飼育環境の隅々にまで反映されているのです。
まず特徴的なのが鶏舎です。
小松さんは野菜栽培用のハウスを鶏舎として改造して使用しています。
これにより、鶏の健康に不可欠な通気性と採光を十分に確保。
鶏舎内部には、鶏が自然な行動をとれるように止まり木が設けられ、鶏が立体的に空間を利用できるように配慮されています。
1つの鶏舎あたりの飼養羽数は50羽から60羽程度が目安とされますが、はたやま夢楽では1つの小屋あたり約50羽と、鶏がストレスを感じにくいようスペースの広さも細かく調整されています。
飼育の基本スタイルは、鶏舎と屋外の放飼場を組み合わせた「放し飼い」です。
鶏たちは日中、太陽の光が降り注ぐ放飼場で自由に地面をつつき、砂浴び(土浴び)をします。
この土浴びは鶏にとって非常に重要で、羽の汚れを落としたり、寄生虫を防いだりするだけでなく、ミネラルや微生物を摂取して体調を整える効果もあると考えられています。
小松さんの鶏舎では、地元畑山の土を適宜補充し、鶏が常に新鮮な土に触れられるようにしています。
ただし、雨天時や地面が濡れている場合、また鳥インフルエンザのリスクが高まる冬期(11月~3月頃)には放飼を中止するなど、鶏の安全と健康を最優先した管理が行われます。
飼料にも徹底したこだわりがあります。
与えられる穀物飼料は、PHF(ポストハーベストフリー:収穫後に農薬を使用していない)であり、かつ非遺伝子組換え(Non-GMO)のものが指定されています。
とうもろこしや大豆を主原料とし、さらに緑餌(りょくじ)の給与が必須です。
カボチャ、ピーマン、ブロッコリー、ニンジン、柿の皮、ダイコンの葉など、自家栽培の野菜や野菜くず、野草など多岐にわたる緑餌を1羽あたり1日30g以上(生草換算で約100g)与えています。
これらの緑餌は、鶏の健康維持はもちろん、卵黄色を濃く鮮やかにし、肉質にも良い影響を与えます。
このような細やかな配慮と手間こそが、土佐ジローの卓越した品質を生み出す秘訣なのです。
アニマルウェルフェア、つまり動物福祉の観点からも、鶏たちがストレスなく、その習性を発揮できる環境づくりが徹底されています。
限界集落に光!土佐ジローと畑山の未来
小松靖一さんの土佐ジロー生産への情熱は、単に美味しい鶏を育てることだけに留まりません。
その根底には、自身の故郷である高知県安芸市畑山地区への強い想いと、深刻な過疎化に歯止めをかけたいという願いがあります。
畑山地区は、報道時点で人口約20名という、いわゆる限界集落です。
しかし、小松さんはこの地で土佐ジローを核とした産業を興し、地域に新たな活気をもたらしています。
具体的には、生産した土佐ジローを味わえる宿泊施設兼飲食店「はたやま憩の家」を運営。
ここでは、土佐ジローの炭火焼きをはじめとする料理を提供し、生産(1次産業)から加工・販売・サービス(2次・3次産業)までを一貫して手がける「6次産業化」を実践しています。
この取り組みにより、地域に雇用を生み出すとともに、年間3000人もの観光客を呼び込むことに成功しました。
小松さんが生産する土佐ジローの卓越した品質は評判を呼び、県内外の焼き鳥専門店の店主や料理人たちが、技術研修や情報交換のために視察や合宿に訪れるほどです。
これは、一個人の努力が地域ブランド全体のイメージ向上に大きく貢献している素晴らしい事例と言えます。
情報発信にも積極的で、元新聞記者である妻・圭子さんの広報スキルも大いに活かされています。
公式ブログやSNSを通じた情報発信に加え、老朽化した食肉処理加工場の再建資金を募るためにクラウドファンディングを活用するなど、現代的なコミュニケーション手法も巧みに取り入れています。
土佐ジローは、畑山地区にとって、まさに地域再生の希望の光となっているのです。
プロも絶賛!極上親子丼からアヒージョ
土佐ジローの魅力は、その育て方や生産者の情熱だけに限りません。
実際に食した人々、特に食のプロフェッショナルたちを唸らせる味わいこそが、土佐ジローが特別な地鶏であることの証です。
東京・神楽坂にある焼き鳥の名店では、料理人が土佐ジローの肉質に魅了され、定期的に高知を訪れて仕入れているほどです。
市場に出回る一般的な鶏とは全く異なり、しっかりとした歯ごたえと野趣あふれる風味が、料理の幅を格段に広げる素材として高く評価されています。
番組内では、塚原アナウンサーがその肉を試食し、うま味がじわっと口に広がる肉質と食感の良さに驚きを隠せない様子が伝えられる予定です。
地元高知でも、土佐ジローを使った絶品料理が楽しめます。
高知市にある和食居酒屋では、店主の松井幸二さんが23年前から土佐ジローを使った料理を提供。
看板メニューは、土佐ジローの卵と肉をふんだんに使った親子丼です。
卵の濃厚さと肉のコクが見事に調和し、丁寧に炊き上げたご飯と香ばしいだしが絶妙な一体感を生み出します。
その味わいは観光客にも人気で、リピーターが後を絶ちません。
さらに、土佐ジローの可能性は、もも肉やむね肉といった主要な部位だけに留まりません。
高知市の料理人・山本巧さんは、一般にはあまり知られていない内臓やトサカといった希少部位を活かし、アヒージョや独創的な創作料理を提供しています。
肝、砂肝、トサカなどを独自の方法で調理したアヒージョは、香ばしくお酒との相性も抜群です。
こうした先進的な取り組みは、「土佐ジローの会」というイベントで発表され、県内の料理人たちが技術と発想を共有し、互いに刺激し合う場となっています。
余すことなく命をいただくという理念に基づいた調理方針からも、土佐ジローが単なる食材ではなく、地域の食文化を豊かにする存在であることが伝わってきます。
まとめ:土佐ジローの魅力と生産者の熱意について
高知県安芸市で育まれる地鶏「土佐ジロー」は、その血統、手間暇をかけた飼育法、そして生産者の情熱が生み出す、まさに極上の味わいです。
小松靖一さんご夫妻の「鶏を鶏らしく育てる」という哲学は、畑山地区の自然豊かな環境の中で、鶏本来の生命力を最大限に引き出し、その結果として得られる肉質・卵質は多くの人々を魅了しています。
地域活性化への貢献や、料理人たちによる新たな食の可能性の追求など、土佐ジローが持つ物語はこれからも続いていくことでしょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
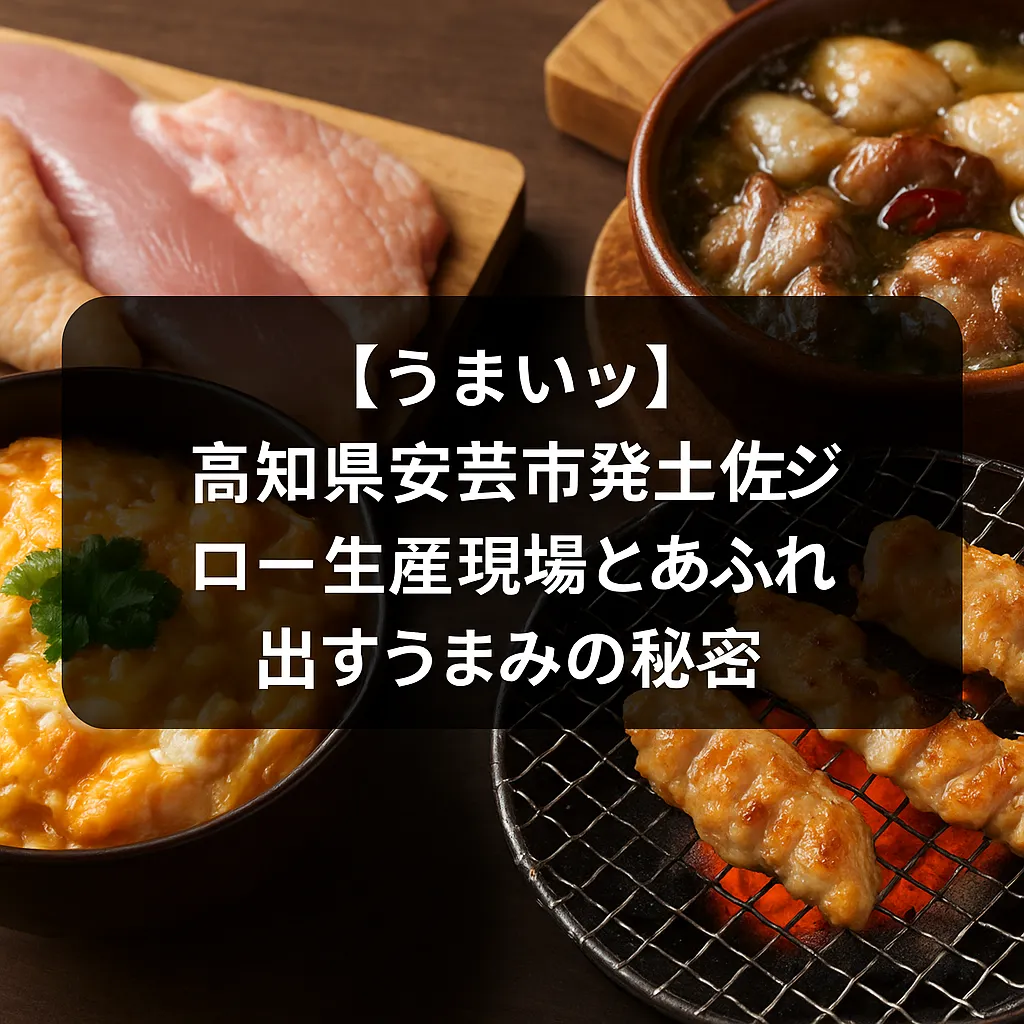



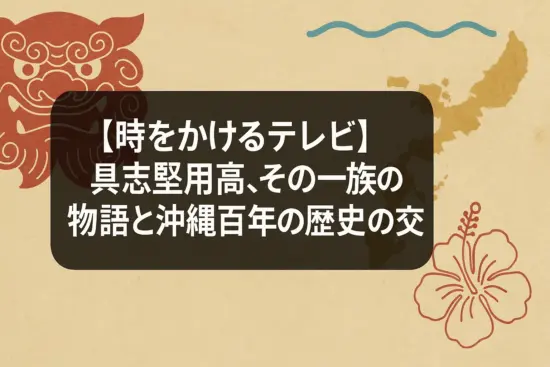
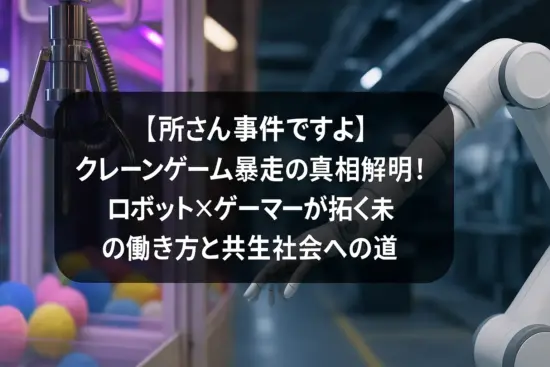

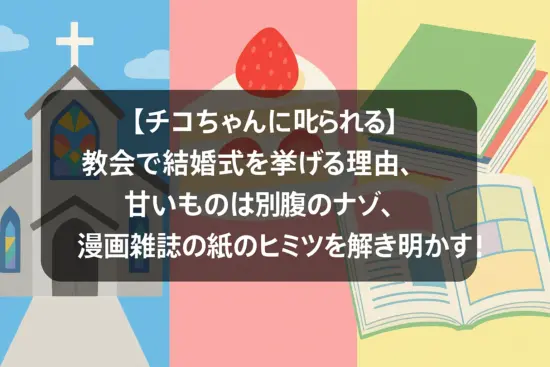

コメント