2024年4月27日に放送された人気番組「相葉マナブ」。
その中の企画「教えて栗原はるみ先生~お花見弁当~」で、料理研究家の栗原はるみさんが紹介した特別なレシピが話題を集めています!
レシピ名は「母ドーナツ」。
その名の通り、栗原先生がお母様から受け継いだ、あるいは思い出から生まれたという、愛情がたっぷり詰まったドーナツです。
この記事では、番組で紹介された「母ドーナツ」の魅力に迫ります。
どんな背景があり、どのような材料が必要で、どうやって作るのか、初心者の方にも分かりやすく解説します。
お花見シーズンのお弁当にも最適な、心温まるドーナツのレシピを知りたい方は必見です。
読み終わる頃には、きっとご家庭で再現してみたくなるはずですよ!
感動の味!相葉マナブ・栗原はるみの「母ドーナツ」とは?
栗原はるみ先生が「相葉マナブ」で心を込めて紹介した「母ドーナツ」。
多くの視聴者がその温かい名前に心惹かれたことでしょう。
このドーナツは、単なるお菓子レシピというだけでなく、栗原先生の個人的な背景と深い愛情が込められた、特別な一品なのです。
この「母ドーナツ」は、栗原先生にとって非常に大切な、家庭の味を受け継ぐレシピです。
文字通り「母のドーナツ」であり、先生自身の母親から教わった味、もしくは母親との温かい思い出にインスピレーションを得て生まれたドーナツだからです。
レシピの名前自体から、世代を超えて受け継がれる家庭料理の温かさや、愛情が伝わってきますね。
番組の「教えて栗原はるみ先生~お花見弁当~」という企画で紹介されたことからも、このドーナツの特性がうかがえます。
お花見のような屋外での食事シーンで楽しまれることを想定しているため、持ち運びが容易で、時間が経っても美味しさが損なわれにくい、つまり冷めても美味しく食べられるように作られています。
見た目も、洗練されたパティスリーのものとは一線を画し、どこか懐かしさを感じさせる素朴で心温まる雰囲気。
手軽に作れるのに、食べる人の心まで満たしてくれる、そんな素敵な家庭の味なのです。
意外と簡単?母ドーナツの全材料リスト
「母ドーナツ」を作るにあたって、「特別な材料が必要なのでは?」と心配されるかもしれませんが、ご安心ください。
結論から言うと、特別な材料は一切必要ありません。
ほとんどの材料が、普段利用しているスーパーマーケットなどで手軽に揃うものばかりです。
これは、栗原はるみ先生の料理哲学が反映されているからです。
先生のレシピは、常に家庭で作りやすいように考え抜かれており、この「母ドーナツ」も例外ではありません。
誰もが気軽に挑戦できるよう、身近な材料で美味しく作れるように工夫されています。
それでは、具体的な材料を見ていきましょう。
- 生地の粉類 : 薄力粉、甘さを加えるための砂糖(グラニュー糖など)、生地を膨らませるベーキングパウダー、そして味を引き締めるための塩が少量必要です。これらは、多くのお家庭で常備されている基本的な粉類ですね。
- 生地の液体類 : 卵、そして牛乳または水、さらに風味としっとり感をプラスするための溶かしバターまたはサラダ油を使用します。牛乳を使うか水を使うか、バターを使うか油を使うかで、最終的なドーナツの風味や食感(バターなら風味豊か、油なら軽めなど)が少し変わってきます。
- 仕上げ用 : 揚げたドーナツの美味しさを引き立てるための仕上げ材もシンプルです。定番のグラニュー糖、あるいは和風テイストを楽しめる、きな粉と砂糖を混ぜ合わせたものを用意します。どちらを選ぶかで、ドーナツの最終的な風味が決まります。
- 揚げ油 : ドーナツを揚げるための揚げ油が適量必要になります。サラダ油など、普段お使いのもので大丈夫です。
これらの材料リストからも分かるように、特別な専門店に行かなければ手に入らないような珍しい食材は含まれていません。
「母ドーナツ」という名前が持つ「家庭的」「手軽さ」といったイメージ通り、思い立ったらすぐにでも挑戦できる手軽さが、このレシピの大きな魅力の一つと言えるでしょう。
感動の味を再現!母ドーナツの作り方ステップ
材料がシンプルなだけでなく、作り方も非常に分かりやすく、基本的なポイントを押さえれば、お菓子作り初心者の方でも美味しい「母ドーナツ」を再現することが可能です。
複雑な工程や特別な技術は必要なく、家庭でのお菓子作りの基本が詰まったような手順となっています。
ただし、いくつかの簡単なコツを守ることが、栗原先生が意図した美味しさを引き出すための秘訣となります。
さっそく、具体的な作り方のステップを見ていきましょう。
- 粉類の準備
- 混ぜ合わせ : まず、生地のベースとなる粉類を準備します。ボウルに薄力粉、砂糖、ベーキングパウダー、そして塩(もしあれば)を入れて、泡だて器などでよく混ぜ合わせます。この段階で粉類をふるっておくと、ダマができにくく、材料がより均一に混ざり、結果として軽い食感のドーナツに仕上がります。この最初のひと手間が、後の工程をスムーズに進めるためにも大切です。
- 液体材料の準備
- 混合 : 次に、液体材料を用意します。別の容器(ボウルなど)で卵を溶きほぐし、そこに牛乳(または水)と、風味付けのための溶かしバター(またはサラダ油)を加えて、泡だて器などで均一になるまでしっかりと混ぜ合わせます。卵をあらかじめよく溶いておくこと、液体と油脂をしっかり混ぜておくことが、後で粉類と合わせたときにムラなく混ざるためのポイントです。
- 生地作り
- 混ぜ方注意 : ここが美味しさを左右する重要なステップです。粉類が入ったボウルに、準備しておいた液体材料を一気に加えます。そして、ゴムベラなどに持ち替え、「切るように」さっくりと混ぜ合わせていきます。練らないように注意し、粉気が少し残る程度で混ぜるのを止めるのが最大のコツです。
なぜ混ぜすぎがいけないのかというと、小麦粉に含まれるグルテンが過剰に形成されてしまうからです。
グルテンが出すぎると、ドーナツが硬く、重い食感になってしまいます。
逆に、混ぜるのを最小限に抑えることで、グルテンの形成が抑えられ、ふんわりとした、あるいはさっくりとした軽い食感のドーナツに仕上がるのです。
これは家庭料理の知恵であり、栗原先生の経験に基づいた成功のための秘訣と言えるでしょう。
- 成形
- 形を作る : 生地ができたら、ドーナツの形に成形します。成形方法には主に二つのタイプが考えられます。一つは、打ち粉(分量外の薄力粉)をした台の上で生地をめん棒などで約1cmの厚さに伸ばし、ドーナツ型(丸型と、中心を抜く小さな丸型)で抜く方法です。もう一つは、より簡単な方法として、スプーンを2本使って生地をピンポン玉くらいの大きさにすくい取り、軽く形を整えながら直接油に落とし入れる「ドロップドーナツ」形式です。型抜きの場合は均一な形と火通りが期待でき、スプーンで作る場合はより素朴で手作り感あふれる仕上がりになります。
- 揚げる
- 温度管理 : 成形した生地を揚げる工程です。鍋やフライパンに揚げ油を入れ、160℃から170℃の間の適切な温度に熱します。温度計を使って正確に測るのが理想的です。この温度管理が非常に重要です。温度が低すぎるとドーナツが油を吸いすぎてしまい、油っぽい仕上がりに。逆に温度が高すぎると、表面だけが焦げてしまい、中まで火が通らない「生焼け」状態になる可能性があります。
- 揚げる時間 : 適温になった油に、成形した生地をそっと入れます。一度にたくさんの生地を入れると油の温度が急激に下がってしまうため、数回に分けて揚げるようにしましょう。生地を入れたら、片面あたり2~3分を目安に、時々返しながら全体がきつね色になり、中までしっかりと火が通るまで揚げます。竹串などを刺してみて、生の生地がついてこなければ揚がったサインです。
指定された温度で、適切な時間揚げること。
これが、外はカリッと香ばしく、中はふんわりと軽い、理想的なドーナツに仕上げるための鍵となります。
- 仕上げ
- 油を切る : 揚がったドーナツは、すぐに油から取り出し、網やキッチンペーパーを敷いたバットなどの上に乗せて、余分な油をしっかりと切ります。油切れが悪いと、時間が経った時にべたっとした食感になってしまうことがあります。
- まぶす : ドーナツの油が切れたら、最後の仕上げです。ドーナツがまだほんのりと温かいうちに、用意しておいた仕上げ用のグラニュー糖、またはきな粉と砂糖を混ぜたものを全体にまんべんなくまぶしつけます。ドーナツが温かいうちに行うのがポイント。表面に残る熱とわずかな湿気によって、砂糖などが付きやすくなるためです。
この最後のひと手間が、見た目の美しさを高めるだけでなく、食べた時の風味や食感を格段に向上させます。
細部にまで配慮された、完成度を高めるための大切な工程と言えるでしょう。
まとめ:相葉マナブで話題!栗原はるみの母ドーナツについて
今回は、2024年4月27日放送の「相葉マナブ」で料理研究家・栗原はるみ先生が紹介した、愛情たっぷりの「母ドーナツ」のレシピについて詳しくご紹介しました。
特別な材料や難しいテクニックは不要で、家庭にある身近な材料とシンプルな手順で作れる、心温まる味わいのドーナツです。
生地の混ぜすぎに注意し、適切な温度で揚げるのが美味しく作るコツです。
ぜひ、このレシピを参考に美味しいドーナツを作って、ご家族やお友達とのおやつタイム、そしてこれからの季節のお花見弁当などに加えてみてはいかがでしょうか。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
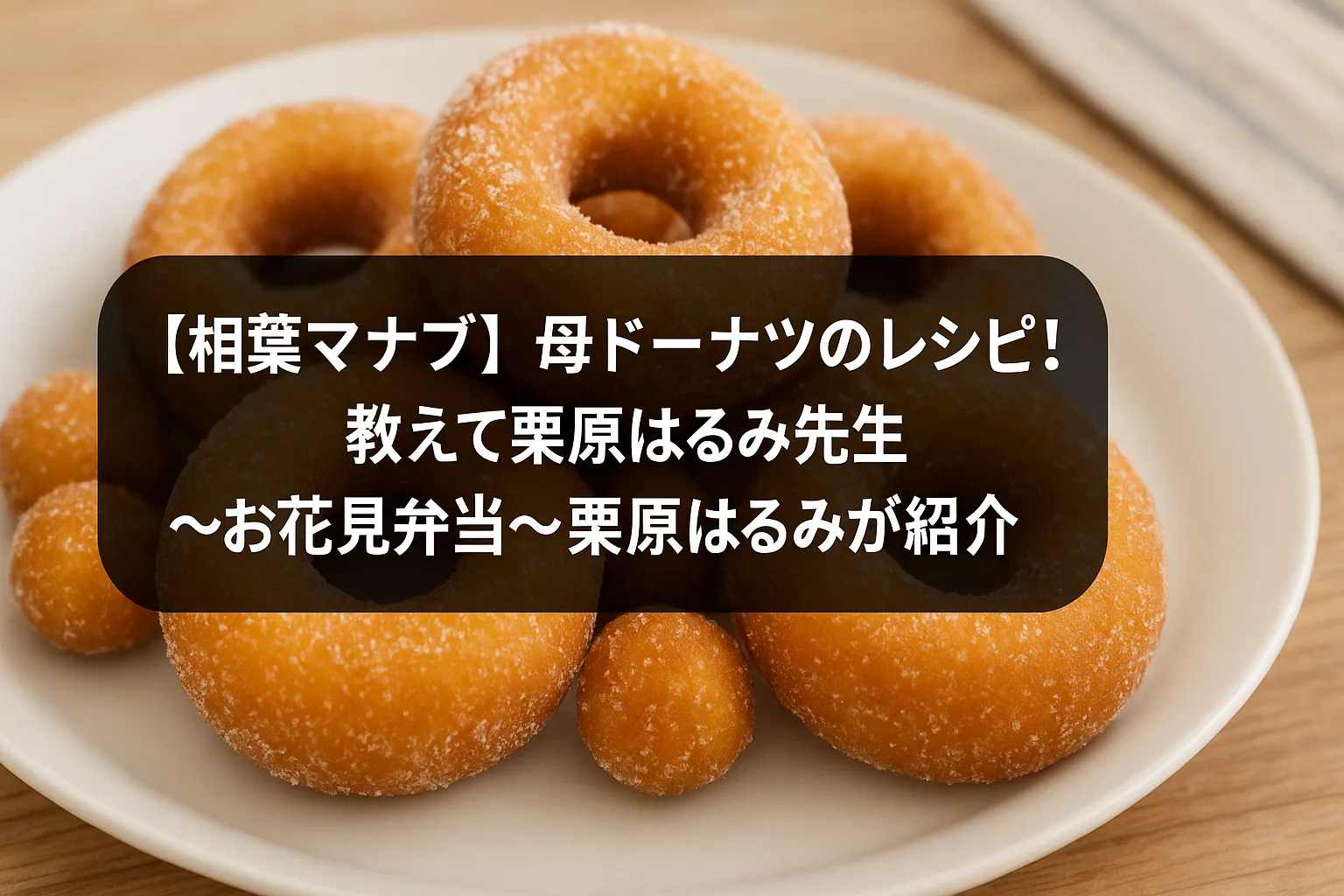








コメント