この記事では、2025年5月4日に放送されたNHK総合の番組『国宝を売り込め!大作戦〜3つの国宝祭りの舞台裏〜』で紹介された、京都・奈良・大阪の三都市同時開催という前代未聞の国宝展について深掘りします。
合計約260点もの国宝が集結した壮大なイベントの見どころはもちろん、普段は目にすることのない国宝輸送の驚きの技術や、美術品の魅力を最大限に引き出す展示の工夫、さらにはフィギュアや人気キャラクターとのコラボといった、国宝を未来へ繋ぐための新しい取り組みまで、その舞台裏のすべてが分かります。
文化財の「保存」から「活用」へとシフトする現代の動きも感じられる内容です。
5/4放送!NHK『国宝を売り込め!大作戦』
まずは、この注目のドキュメンタリー番組について紹介します。
2025年5月4日(日)の16時00分から45分間、NHK総合テレビジョンで放送された『国宝を売り込め!大作戦〜3つの国宝祭りの舞台裏〜』は、日本の文化財、特に国宝に焦点を当てた特別な番組です。
この番組は、京都・奈良・大阪という日本の古都であり文化の中心地で、同時期に開催されている三つの大規模な国宝関連展覧会の裏側に密着しました。
単なる展覧会の紹介に留まらず、この壮大な文化事業を成功させるために費やされた、緻密な計画や高度な専門技術、そして文化財を未来へと継承しようとする関係者たちの熱い想いや努力に光を当てています。
「国宝を売り込め!」という少し刺激的なタイトルには、従来の「保護・公開」という枠を超え、国宝の持つ価値を経済的・広報的な側面からも積極的に引き出し、社会全体でその恩恵を受けようという現代的なアプローチの必要性が込められているのです。
京都・奈良・大阪に国宝260点!空前絶後の展覧会
今回のプロジェクトがいかに特別なものであるか、その規模感から見ていきましょう。
京都、奈良、大阪の三都市にある主要な博物館・美術館が連携し、同時期に国宝関連の大型展覧会を開催するという、まさに前代未聞の試みです。
これらの展覧会を合わせると、なんと約260点もの国宝が一堂に展示されます。
これは日本の美術史上でも例を見ない、驚くべき規模の文化イベントと言えるでしょう。
この壮大な企画が実現した背景には、2025年に開催される大阪・関西万博という国際的なイベントが重要な契機となっています。
単なる個別の展覧会ではなく、万博という舞台に向けて日本の文化発信力を高め、国内外からの観光客誘致や地域活性化にも繋げようとする、国家レベルでの戦略的な取り組みなのです。
大阪は通史、奈良は祈り、京都は交流…三都めぐり
三つの展覧会は、それぞれ独自のテーマと魅力を持っています。
連携して巡ることで、日本美術の奥深さをより立体的に感じられる構成です。
まず、大阪市立美術館で開催されている「日本国宝展」(会期:4月26日~6月15日)は、縄文時代の土偶から江戸時代の絵画まで、各時代を代表する国宝約130件(参考出品除く)をほぼ時代順に展示。
まるで日本美術の教科書を巡るように、壮大な歴史の流れを体感できます。
大阪・関西万博と、約2年半の大規模改修を経た美術館のリニューアルオープンを記念した、大阪初の国宝展です。
次に、奈良国立博物館の「超 国宝展-祈りのかがやき-」(会期:4月19日~6月15日)は、博物館の開館130周年を記念する展覧会です。
テーマは神仏への「祈り」。
法隆寺の「観音菩薩立像(百済観音)」をはじめとする奈良の古寺ゆかりの仏教美術を中心に、国宝約110件、重要文化財約20件が集結。
古代日本の深い精神性に触れることができます。
そして、京都国立博物館の「日本、美のるつぼ―異文化交流の軌跡―」(会期:4月19日~6月15日)も、大阪・関西万博記念展です。
日本美術の歴史を「交流」という視点から捉え直し、大陸や諸外国との出会いから生まれた多様な美を探ります。
俵屋宗達筆「風神雷神図屏風」などの国宝18件(報道によっては19件)を含む約200点が展示され、国際色豊かな作品群を楽しめます。
これら三館は連携しており、例えば相互割引制度を利用して「はしご」することで、「日本美術の時間旅行が完成する」ような体験が可能です。
国宝輸送は超大変!驚きの「大作戦」の裏側
展示室で静かに輝く国宝ですが、そこに至るまでには大変な道のりがあります。
特に「輸送」は、知られざるドラマと技術が詰まったプロセスです。
国宝、とりわけ長い年月を経た美術工芸品は、材質も構造も非常にデリケート。
わずかな振動や衝撃、温度・湿度の変化でも劣化や破損に繋がる可能性があります。
そのため、国宝の輸送は単なる「運搬」ではなく、文化財保護の最前線とも言える極めて専門的な作業なのです。
番組では、この困難な課題に挑む「輸送大作戦」の舞台裏に密着。
そこでは、科学的知見に基づいた様々な技術が駆使されています。
まず、作品一点一点の形状や材質に合わせて、無酸性の薄紙や特注の緩衝材(ポリウレタンフォームや綿など)を用いて丁寧に梱包。
衝撃吸収効果を高める「二重箱方式」が用いられることも多いです。
この作業は「美術品梱包輸送技能取得士」などの専門資格を持つ技術者が担当します。
輸送車両には、路面からの衝撃を吸収するエアサスペンションを備えた美術品専用車両が使われます。
さらに、特殊なコイルばねを用いた防振パレットなども活用し、振動を最小限に抑えます。
輸送ルートも、路面状況などを考慮して最も振動の少ない道が選定されます。
温度・湿度の急激な変化を防ぐため、車両は空調設備を完備。
梱包箱内に温度・湿度を記録するデータロガーを設置し、輸送環境を常にモニタリングします。
そして、国宝という国家的な宝を守るため、盗難やテロなどのリスクに備え、警察車両の伴走やGPS追跡を含む厳重な警備体制の下で輸送が実施されるのです。
番組では、こうした専門技術の粋を集めたプロセスと、そこに携わる人々の緊張感や連携プレーを伝え、展示されている文化財の重みを実感させてくれます。
百済観音の微笑みも再現?プロの展示テクニック
無事に美術館に到着した国宝を、来館者に最も魅力的に見せるのが「展示」の技術です。
ここにも専門家たちの知恵と工夫が凝らされています。
優れた展示は、ただ作品を並べるだけではありません。
作品への深い理解と敬意に基づき、鑑賞者の知的好奇心や感性を刺激する空間を作り出すことを目指します。
その鍵を握る要素の一つが「照明」です。
展示照明は、作品を美しく見せるだけでなく、光による劣化(特に紫外線や過度の明るさ)を防ぐという保存科学的な側面も非常に重要です。
近年、美術館の照明は、従来のハロゲンランプなどからLED(発光ダイオード)へと移行しています。
LEDは省エネ・長寿命なだけでなく、文化財に有害な紫外線や赤外線の放出が少なく、色温度(光の色味)や照度(明るさ)を細かく調整でき、物の色を忠実に再現する能力(演色性)も高いという、文化財展示に適した多くの利点を持っています。
番組では、特に奈良国立博物館で展示される法隆寺の国宝「百済観音像」の照明に注目。
その柔和な表情、いわゆる「微笑み」が効果的に浮かび上がるように、専門の技術者が目元に柔らかく光が当たるよう特別な照明演出を施した様子が紹介されました。
これは、個々の作品の特性を深く理解し、その魅力を最大限に引き出すための照明デザインの一例です。
他にも、作品本来の色味を再現する高演色タイプのLEDの採用や、ガラスケースへの映り込みを避ける照射角度の工夫など、様々な技術が駆使されています。
また、展示ケース自体も進化しており、ガラス表面の反射を極限まで抑える特殊フィルム(モスアイ構造フィルムなど)によって、まるでケースが存在しないかのようにクリアに作品を鑑賞できる環境も実現しつつあります。
壁の色やキャプションの配置なども含め、鑑賞体験全体が慎重にデザインされているのです。
風神雷神フィギュアも!可愛すぎる国宝グッズ
展覧会のもう一つの楽しみといえば、ミュージアムショップのグッズです。
今回の国宝展では、これまでのイメージを覆すようなユニークなグッズも登場しています。
ミュージアムグッズは、来館者にとっては鑑賞の記念品であり、美術館にとっては収入源ですが、同時に文化財への関心を広げる有効なツールでもあります。
近年はデザイン性や独創性が高まり、作品理解を深める工夫も凝らされるようになりました。
今回の国宝展では、特に若い世代やこれまで美術館にあまり馴染みのなかった層にも親しみを持ってもらおうと、意欲的なグッズ開発が行われています。
番組でも注目されたのが、京都国立博物館に展示されている俵屋宗達筆の国宝「風神雷神図屏風」をモチーフにしたフィギュアです。
これはフィギュア制作で有名な株式会社海洋堂が手掛け、著名な造形作家・竹谷隆之氏の工房が造形を担当したもので、国宝という伝統的なモチーフを現代のホビーカルチャーの文脈で捉え直した精巧な立体造形物となっています。
フィギュア以外にも、各館で多様なコラボレーションが展開されました。
大阪市立美術館では、人気イラストレーターの中村佑介氏が描き下ろしたイラストを用いたクリアファイルやタンブラーなどが販売されたほか、人気オンラインゲーム『刀剣乱舞ONLINE』との連携で、ゲームに登場する刀剣に関連する国宝刀剣のパネル展示や限定グッズが登場しました。
奈良国立博物館と京都国立博物館では、人気キャラクター「すみっコぐらし」が公式応援キャラクターに就任し、展覧会限定のコラボグッズが販売されています。
こうした外部のクリエイターや人気コンテンツとの連携は、国宝への入口を広げ、文化財の新しい楽しみ方を提案する現代的なマーケティング戦略と言えるでしょう。
国宝を未来へ!文化財活用の新しいカタチ
今回の三都同時開催展とそれを紹介する番組は、日本の文化財を取り巻く状況が変化していることを示唆しています。
それは「保存」中心から、より積極的な「活用」へと移行しつつある流れです。
歴史的に、日本の文化財保護政策は、まず文化財を守り遺すことに重点が置かれてきました。
しかし近年では、「保存と活用」の両立、さらには「活用」を通じて文化財の価値を社会に還元し、次世代への継承に繋げていこうという方向へとシフトしています。
その背景には、国の政策的な後押しがあります。
例えば、令和2年(2020年)に制定された「文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律」は、文化財を重要な観光資源として明確に位置づけ、その魅力を高めるための整備や情報発信を国が支援するものです。
今回の三都同時開催展は、まさにこの文化財活用政策の具体的な実践例です。
国立文化財機構が進める、機構所蔵の文化財を各地の博物館へ貸し出す「所蔵品貸与促進事業」の理念を、かつてない規模で実現したプロジェクトでもあります。
大阪・関西万博という世界的なイベントを絶好の機会と捉え、日本の文化の粋である国宝を大規模に公開することで、国内外に向けて日本の文化発信力を強化し、文化観光を促進しようという国家的な意図がうかがえます。
NHKの番組タイトルにある「売り込め!」という言葉は、こうした文化財の価値を再定義し、より能動的に社会へ発信していくという、新しい時代の文化戦略を象徴しているのかもしれません。
もちろん、過度な商業主義に陥らず、文化財本来の価値を守りながら活用していくバランス感覚が重要になるでしょう。
まとめ:三都同時開催国宝展と文化財活用の未来について
今回は、NHK『国宝を売り込め!大作戦』で紹介された、京都・奈良・大阪での三都同時開催国宝展について、その概要から輸送・展示の舞台裏、そしてフィギュアやキャラクターコラボといった新しい文化財活用の動きまで幅広くご紹介しました。
前例のない規模の展覧会は、日本の美術や歴史に触れる絶好の機会であると同時に、文化財を守り、未来へ伝えていくための専門家たちの努力と、時代の変化に応じた新しい取り組みを知るきっかけにもなります。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
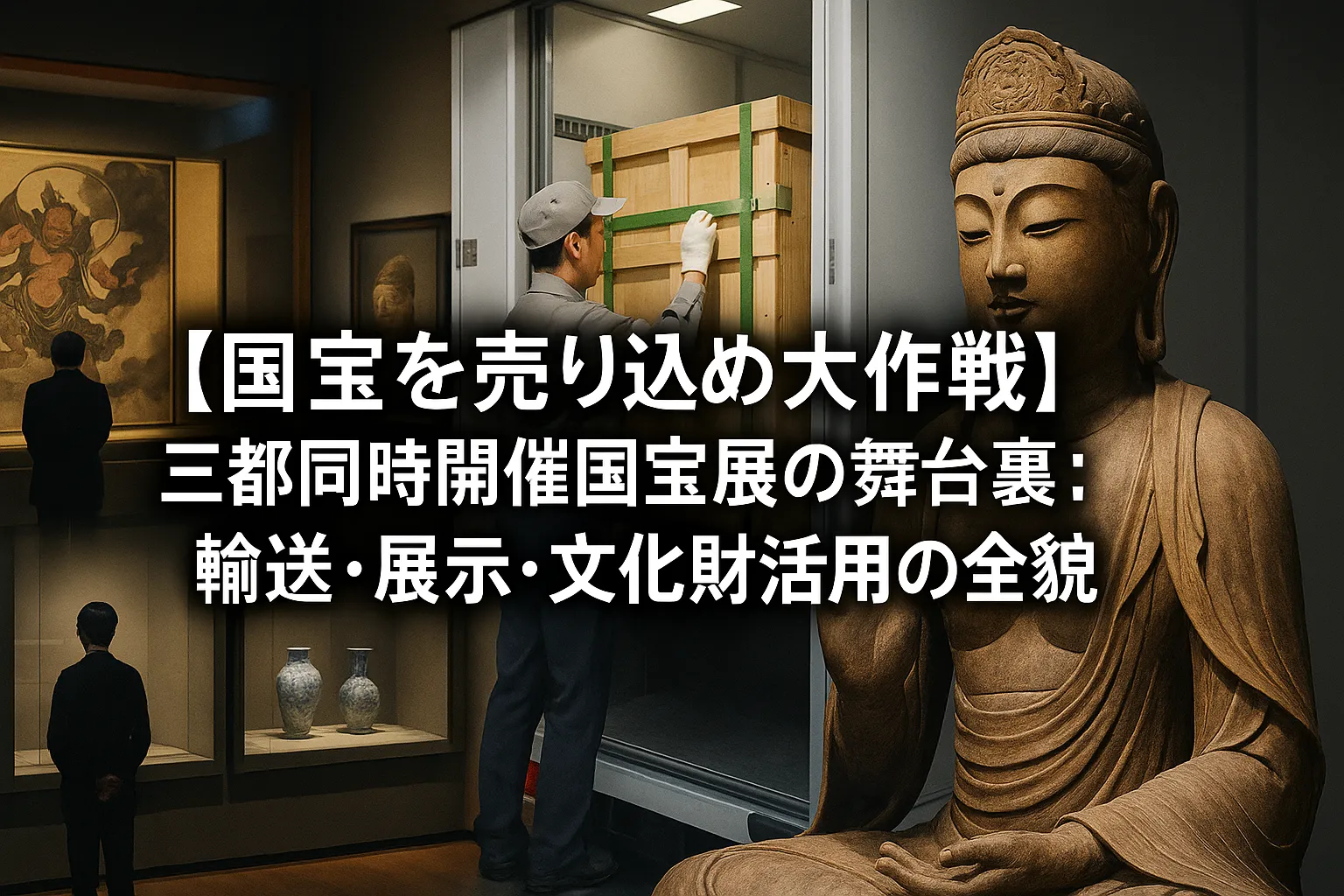








コメント