NHK総合のドキュメンタリー番組『新プロジェクトX〜挑戦者たち〜』で2025年5月17日に放送された「島に誇りを 〜アートでよみがえった瀬戸内海〜」では、瀬戸内海に浮かぶある島が、アートと教育の力によって劇的な再生を遂げる物語が特集されました。
この記事では、かつて産業の衰退や環境問題に苦しみ、「ゴミの島」とまで呼ばれた島が、どのようにして世界中から注目を集める文化的な目的地へと変貌を遂げたのか、その軌跡を深掘りします。
教育系企業が主導した前例のないプロジェクトの核心に迫り、アートホテルの建設、古民家再生、そして子どもたちが主役となった「CPOプロジェクト」といった主要な取り組み、さらには挑戦者たちの情熱や島民との間に生まれた葛藤と信頼の物語を通じて、地域再生の新たな可能性と、そこに暮らす人々の心に灯された希望の光を明らかにしていきます。
新プロジェクトX「島に誇りを 〜アートでよみがえった瀬戸内海〜」
この放送回では、一見不可能とも思える状況から、地域が持つ潜在的な力と外部からの革新的なアイデアが融合し、新たな価値を創造していくダイナミックな過程が描かれました。
それは単なる経済復興の物語ではなく、文化と教育を通じて人々の心に誇りを取り戻し、コミュニティそのものを再生させていく挑戦者たちのヒューマンドラマです。
「ゴミの島」と呼ばれた絶望から、奇跡の再生が始まる
プロジェクトが始まる前の島々は、深刻な問題を抱えていました。
主要産業であった漁業は衰退の一途をたどり、若者たちは次々と島を離れ、過疎化と高齢化が急速に進んでいました。
観光客の姿もまばらで、島全体が活気を失っていたのです。
さらに、海は「瀕死」と形容されるほど汚染され、山は木々を失い「はげ山」となり、沿岸部には処理しきれないゴミが打ち寄せられ「ゴミの島」とまで呼ばれる始末でした。
この状況は、高度経済成長期以降の産業活動の負の遺産であり、直島町の人口は昭和50年(1975年)から平成27年(2015年)までの40年間で実に44.4%も減少したというデータが、その深刻さを物語っています。
経済的な困窮は島民の心にも影を落とし、地域への愛着や自信、未来への希望といった無形の価値までもが失われかけていたのです。
教育企業の大胆な挑戦:アートホテルと立ちはだかる壁
このような状況に一石を投じたのが、岡山市に本社を置く教育関連企業、ベネッセホールディングス(旧福武書店)とその関連公益財団法人福武財団でした。
「瀬戸内海の島に世界中の子どもたちが集える場を作りたい」という創業者・福武哲彦氏の夢と、当時の直島町長・三宅親連氏の「教育的な文化エリアを開発したい」という想いが共鳴し、プロジェクトは始動します。
哲彦氏の遺志を継いだ息子の福武總一郎氏は、現代アートを核とした壮大な地域再生ビジョンを掲げ、「Benesse = よく生きる」という企業理念を島で実践しようとしました。
その最初の大きな一歩が、1992年にオープンした建築家・安藤忠雄氏設計の「ベネッセハウス」です。
これは、宿泊施設と美術館が一体となった、自然と建築、アートの共生を目指す画期的な施設でした。
しかし、その道のりは決して平坦ではありません。
オープン当初、宿泊客はほとんど訪れず、ホテルの運営は赤字続きでした。
高額な宿泊料金、現代アートへの馴染みの薄さ、そして交通の不便さが大きな壁となったのです。
さらに深刻だったのは、地元住民の無関心と不信感でした。
「よそ者のやっていること」という距離感は埋まらず、企業側と島民との間にはほとんど交流がない状態が続きました。
企業が思い描く理想と、島が抱える現実との間には大きな隔たりがあったのです。
それでも企業側は諦めず、長期的な視点を持ってプロジェクトを推進し続けました。
起死回生!「古民家アート」が島と人の心を変えた
プロジェクトが大きく動き出すきっかけとなったのは、1998年に始まった「家プロジェクト」でした。
これは、直島の本村地区に点在する、長年放置され朽ちかけていた古民家を、アーティストが空間全体を作品として再生するという大胆な試みです。
例えば、宮島達男氏の「角屋」では、約200年前に建てられた家屋の暗闇に浮かぶ水面に、島民が設定した速度で明滅するLEDカウンターが設置され、地域の時間と歴史を刻みます。
ジェームズ・タレル氏の「南寺」では、安藤忠雄氏設計の建物内で光を体験し、鑑賞者の知覚に変化を促します。
これらの古民家アートは、建物の歴史や暮らしの痕跡と現代アートが見事に融合し、美術館では味わえない唯一無二の体験を生み出しました。
この「家プロジェクト」がSNSなどを通じて国内外に拡散されると、「見てみたい」「行ってみたい」という人々が島を訪れるようになり、静かだった島に少しずつ活気が戻り始めました。
そして何よりも大きな変化は、島民の心に起こりました。
「誰も来ない」「何もない」と思っていた自分たちの島に多くの人が訪れ、その風景や文化に感動する姿を目の当たりにし、住民たちの中に地域への誇りが芽生え始めたのです。
自主的に案内看板を作成したり、空き家を改装してカフェや宿泊所を始めたりする人も現れ、アートプロジェクトは島民を巻き込みながら展開していきました。
子どもたちが未来を紡ぐ!「CPOプロジェクト」の希望
この地域再生プロジェクトにおいて、特に注目されるのが、子どもたちがまちづくりに主体的に関わる「CPOプロジェクト」と呼ばれる一連の教育連携活動です。
これは、教育企業が主導するプロジェクトならではの取り組みで、「学び」を核に据え、子どもたちが自らの視点で地域を見つめ直し、未来を創造していく力を育むことを目指しています。
具体的には、地元の小中学校と連携し、総合学習の時間などを通じてアートについて学んだり、小学5年生が英語で本村地区を案内する「Meet the World」プログラムを実施したりしています。
また、子どもたちが島の未来を考え、新しい家プロジェクトを提案するようなワークショップも開催されました。
これらの活動を通して、子どもたちは自分たちの住む島を深く理解し、その魅力を発信する役割を担います。
例えば、子どもたちが制作した「島めぐりマップ」は、地元の人しか知らない小道やおすすめの風景が盛り込まれ、観光客から「わかりやすい」「あたたかみがある」と好評を得ています。
島で育つ子どもたちが故郷に誇りを持ち、未来の担い手として成長していく。
その姿は大人たちにも刺激を与え、地域全体に希望の輪を広げています。
「CPOプロジェクト」は、Child/Citizen Participation & Ownership(子ども・住民の参加と主体性)の理念を体現するものであり、持続可能なまちづくりのモデルとして全国からも注目を集めています。
アートが問いかける「よく生きる」:瀬戸内の挑戦は続く
瀬戸内海の島々で展開されるアートプロジェクトは、単なる観光客誘致や経済効果だけを追求するものではありません。
その根底には、ベネッセの企業理念である「よく生きる (Benesse)」とは何かを問い続ける哲学が存在します。
福武總一郎氏は、この地に既存の宗教を超える普遍的な「聖地」を創り、人々がアートや自然、建築との対話を通じて内省し、「自然の中で生かされる」ことを考える場を提供したいという壮大な構想を抱いてきました。
それは、経済的な豊かさだけではない、人間らしい生き方や幸福とは何かを追求する試みです。
30年以上にわたる長期的なビジョンと継続的な投資によって、プロジェクトは数々の困難を乗り越え、世界的な評価を得るに至りました。
年間100万人を超えるとも言われる観光客が訪れるようになり、島の活性化に大きく貢献しました。
しかしその一方で、観光客急増による交通インフラへの負荷や住民生活への影響(オーバーツーリズム)、経済効果の島外流出や仕事の種類の偏り、現代アートに対する世代間の意識のギャップといった新たな課題も生まれています。
それでもこのプロジェクトは、新たなギャラリーのオープンや美術館計画など、常に進化を続けています。
アートを通じて地域と人々の未来を問い続けるこの挑戦は、私たちに「地域とは何か」「人が生きるとは何か」を深く考えさせる、終わりなき物語なのです。
まとめ:瀬戸内アート再生が示す希望について
瀬戸内海の島々で展開されたアートによる地域再生プロジェクトは、教育と文化の融合がもたらす大きな可能性を示しています。
挑戦者たちの情熱と島民の変容、そしてアートが持つ力が、衰退した地域に新たな命を吹き込み、世界に誇れる場所へと生まれ変わらせました。
この物語は、困難な状況にあっても希望を失わず、未来を切り拓くことの大切さを教えてくれます。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
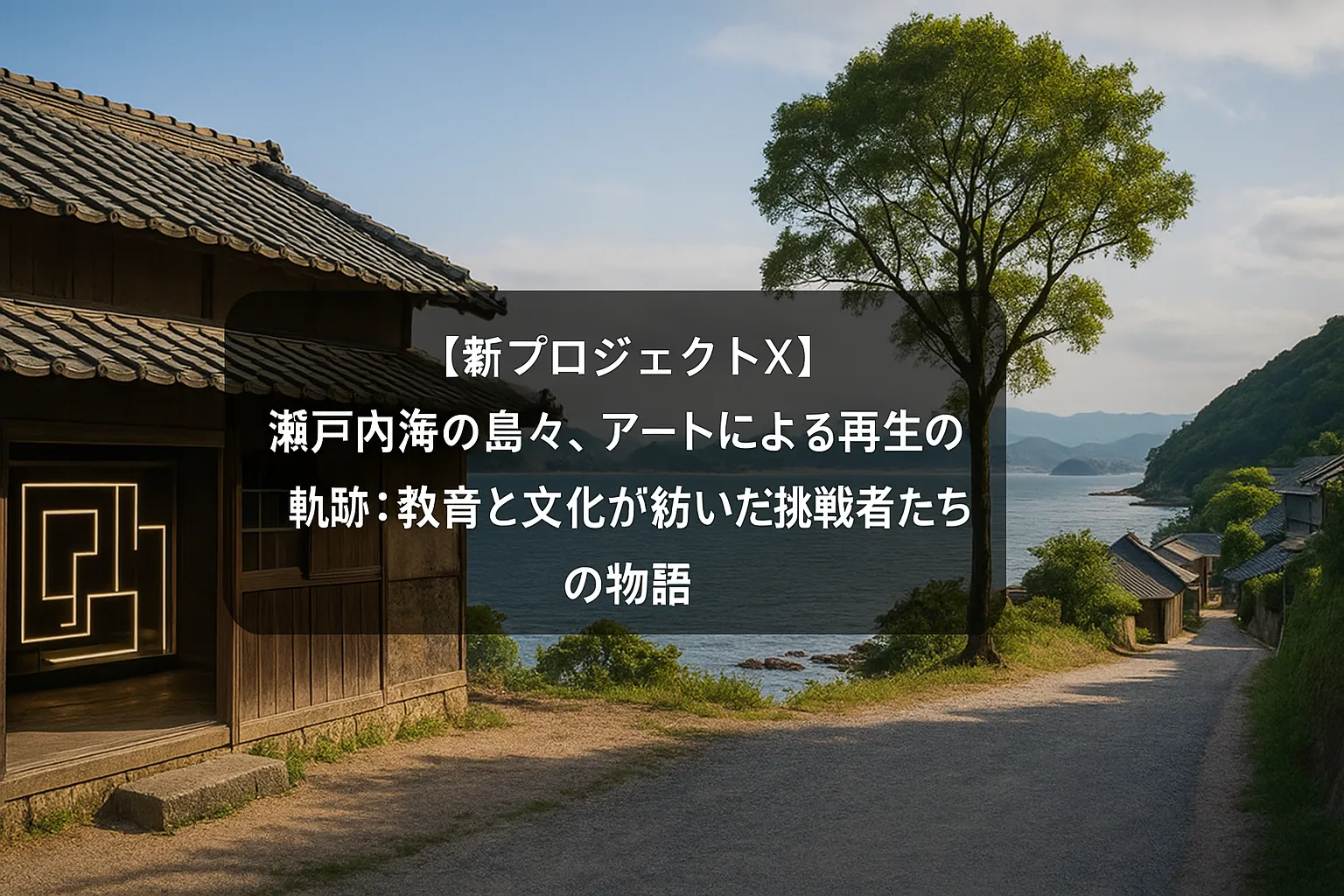



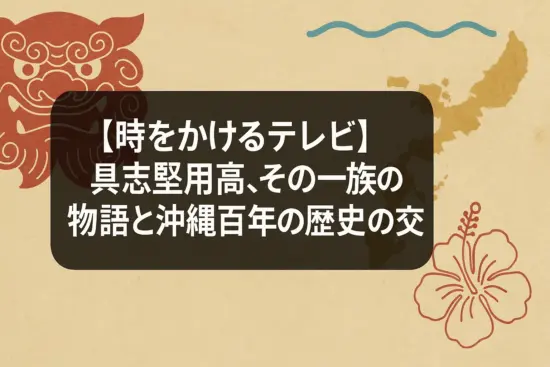
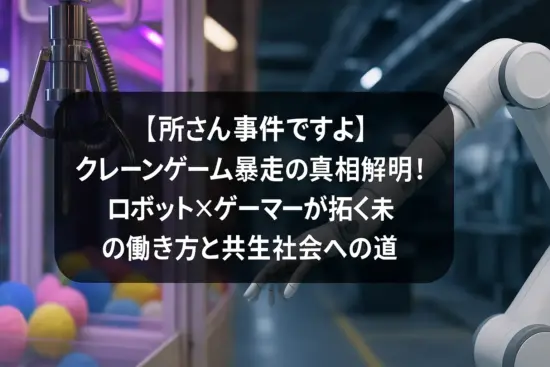

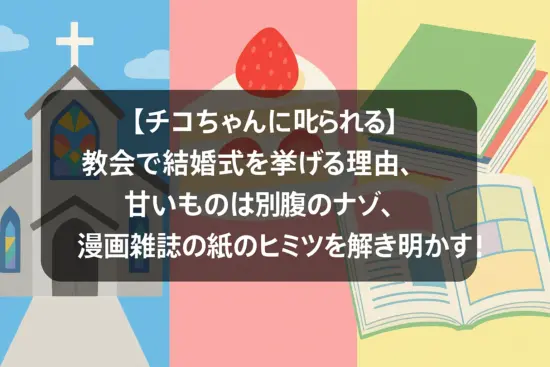

コメント