NHK Eテレの番組「おとな時間研究所」で特集された「朗読を楽しむ」というテーマは、多くの大人世代にとって新たな趣味や自己表現の扉を開くきっかけとなるかもしれません。
この記事を読めば、2025年5月9日に放送されたこの番組が、なぜ今「朗読」に光を当てたのか、その奥深い世界と魅力、そしてプロが伝授する表現の極意が分かります。
人気の朗読教室の様子から、スタジオでの実践的なテクニック、さらには朗読がもたらす心身への良い影響まで、朗読の多面的な価値を初心者にも分かりやすく紐解いていきます。
声で物語を紡ぐことの楽しさ、そしてそれが日常をどう豊かにしてくれるのか、そのヒントが見つかるはずです。
おとな時間研究所「朗読を楽しむ」放送概要
2025年5月9日金曜日の20時00分から20時45分まで、NHK Eテレで放送された「おとな時間研究所『朗読を楽しむ』」は、成熟した大人世代の知的好奇心に応える教養番組です。
この回では、静かなブームとなっている朗読の魅力、基本技術、そして多様な楽しみ方が、教室取材、スタジオ指導、出演者による実演を通じて紹介されました。
主要な出演者は、朗読教室講師の松浦このみ氏、NHKラジオ「ラジオ深夜便」アンカーの高橋淳之氏、そして司会を務める俳優の常盤貴子氏とNHKアナウンサーの杉浦友紀氏です。
人気教室に潜入!松浦このみ流、声の表現力とは?
番組前半では、順番待ちが出るほど人気だという松浦このみ氏主宰の朗読教室「gusuto de piro」の様子が紹介されました。
この教室で松浦氏が最も大切にしているのは、一人ひとりの「個性を生かす朗読」です。
松浦このみ氏は、静岡FM放送(K-MIX)のアナウンサーとしてキャリアをスタートさせ、フリーランスとしてTokyo FMなど多くのラジオ番組でパーソナリティを務めた経験豊かな方です。
ナレーターとしても活躍し、2009年から一般向けの朗読教室を開講しています。
教室名「gusuto de piro」はエスペラント語で「梨の味」を意味し、梨のように複雑で豊かな味わいを持つ、五感をフルに発揮して楽しめる朗読を目指しています。
そのため、20代から70代まで、プロ・アマ問わず多様な受講生が集い、それぞれの持ち味を活かした表現を追求しています。
授業では、朗読未経験者でも安心して取り組めるよう、声を出す上での基本的な姿勢や呼吸法といった初歩から丁寧に指導が行われます。
特に繰り返し強調されるのは、「息の通る声をつくる」「意味の区切りを理解して読む」「聞き手を意識する」という3つの基本原則です。
これらは、朗読の普遍的な基礎技術であり、単なる音読から「伝える朗読」へと進化させるための核となります。
受講者は自分の読みを録音して確認したり、講師のフィードバックを熱心にメモしたりと、主体的に学ぶ姿が見られました。
高橋淳之アナ直伝!心に響く「伝える声」の秘訣
番組中盤のスタジオには、NHKラジオ「ラジオ深夜便」のアンカーとして長年活躍する高橋淳之氏が登場し、その豊富な経験に裏打ちされた朗読技術を惜しみなく披露しました。
高橋氏が説くのは、単に文字を読むのではなく、言葉の奥にある感情や情景を「声で届ける」ことの重要性です。
高橋淳之氏は1975年にNHKに入局後、各地の放送局でアナウンサーとして活躍し、2011年からは「ラジオ深夜便」のアンカーを務める、まさに声のプロフェッショナルです。
番組放送時点で73歳というキャリアが、その言葉に重みを与えます。
高橋氏の朗読哲学の中心は、「『読む声』ではなく『伝える声』という意識を持つこと」にあります。
この意識が、聴き手の心に深く響く表現を生み出すのです。
スタジオでは、この「伝える声」を実現するための具体的な技術として、「姿勢」「発声」「感情表現」という3つの基本要素が、実演を交えながら分かりやすく解説されました。
例えば、「姿勢」では背筋を伸ばし呼吸の通り道を確保すること、「発声」では口の開け方や声の響かせ方を意識し聞き取りやすさを高めること、そして「感情表現」では声の抑揚や間の取り方、話す速度の緩急を巧みに使い分けることなどが挙げられます。
これらの技術を駆使することで、聴き手が自然と物語の情景を思い浮かべ、登場人物の心の動きを感じ取れるようになると高橋氏は語ります。
常盤貴子・杉浦アナも挑戦!童話朗読で新たな発見
番組の後半では、司会を務める俳優の常盤貴子氏とNHKアナウンサーの杉浦友紀氏、そしてゲストの高橋淳之氏の3人が、実際に童話の朗読に挑戦しました。
この実践パートは、それまでに学んだ基本技術が実際の作品解釈や表現にどう結びつくのかを具体的に示す貴重な機会となりました。
常盤貴子氏は過去にナレーションやラジオ朗読の経験があり、杉浦友紀アナウンサーも日々声と言葉に携わるプロです。
しかし、この番組では彼女たちも一学習者として朗読に取り組み、その過程での発見や戸惑い、そして上達していく様子が映し出されました。
俳優、アナウンサー、ラジオパーソナリティという異なる専門分野で活躍する3人が、同じ童話をどのように読み解き、声で表現するのか、そのアプローチの違いも見どころの一つでした。
子供の頃に親しんだ物語も、経験豊かな大人の声と解釈によって丁寧に読まれることで、全く新しい物語の世界が広がる可能性が示唆されました。
これは朗読が持つ創造的な側面であり、完成された模範演技としてではなく、挑戦の過程として描かれることで、視聴者自身の試行錯誤を勇気づける効果も期待できます。
この「共感可能な学習者」の姿は、朗読への心理的なハードルを下げ、多くの人々にとって「自分にもできるかもしれない」と感じさせる力を持っています。
なぜ今ブーム?朗読が持つ自己表現と癒やしの力
デジタルコミュニケーションが主流となり、情報が瞬時に消費される現代において、人の声というアナログな媒体を通して言葉を伝える「朗読」が、特に大人世代を中心に静かなブームとなっています。
この背景には、自己表現への根源的な欲求や、情報過多の時代における精神的な充足感への希求があると考えられます。
朗読の魅力は多岐にわたります。
まず、自分の声で物語の世界を立ち上げ、登場人物の喜怒哀楽を追体験することは、大きな「自己表現の喜び」に繋がります。
また、作品を通じて他者の感情や経験に触れ、聞き手の心に寄り添うことで、「他者との共感」が生まれます。
番組で紹介された朗読ボランティアを目指す女性のように、誰かの役に立ちたいという思いが朗読の原動力となることもあります。
さらに、朗読は聞き手の「想像力を刺激し、作品世界を深掘りする体験」を提供します。
声に出して読むことで、作品の情景や登場人物の心理をより具体的に想像し、解釈する必要が生じ、作品への理解が格段に深まります。
そして、朗読は「心身のウェルビーイング」にも良い影響を与える可能性が指摘されています。
腹式呼吸を用いた発声は自律神経を整えリラックス効果が期待でき、しっかりと声を出す行為はストレス軽減にも繋がります。
また、滑舌の訓練や表情筋の運動は口腔機能の維持・向上に、脳科学的には前頭前野の活性化による記憶力向上や認知症予防にも繋がる可能性が示唆されています。
声で紡ぐ豊かな時間:朗読が広げる新しい楽しみ方
NHK Eテレ「おとな時間研究所『朗読を楽しむ』」は、朗読が単なる技術習得や趣味の域を超え、日々の生活の中に新たな発見や感動をもたらす「豊かな時間」を創造する手段であることを教えてくれます。
忙しい日常の中で、一つの作品とじっくり向き合い、言葉の響きや意味を味わいながら声に出して読む行為は、貴重な「立ち止まる時間」を提供します。
「自分の声をもっと活かしたい」「表現力を磨きたい」「誰かの心に届く声を届けたい」といった願いを持つ人々にとって、朗読はその実現の一助となるでしょう。
番組で紹介された朗読教室での学びや、地域に根差したボランティア活動などを通じて、より多くの人々が朗読の魅力に触れ、生活に取り入れていく流れは今後も発展していくと期待されます。
朗読が持つ可能性は、教育現場での言語能力育成、医療・福祉分野でのQOL向上や精神的ケア、さらには地域コミュニティの活性化や文化継承など、より広範な社会的課題への貢献も期待されています。
NHK Eテレのような公共放送が朗読の価値を発信し続けることで、生涯学習の一環としての重要性はさらに高まるでしょう。
声で紡がれる物語は、これからも私たちの心と社会を豊かにし続けていくに違いありません。
まとめ:声で紡ぐ物語が日常を豊かにする魅力について
NHK Eテレ「おとな時間研究所『朗読を楽しむ』」では、朗読が持つ多面的な魅力と、初心者でも始められる具体的な方法が紹介されました。
人気講師の指導法からプロの技術、そして朗読がもたらす心身への好影響まで、その奥深さに触れることで、新たな趣味や自己表現の可能性が広がります。
声に出して物語を読むというシンプルな行為が、私たちの日常に彩りと深みを与えてくれるでしょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
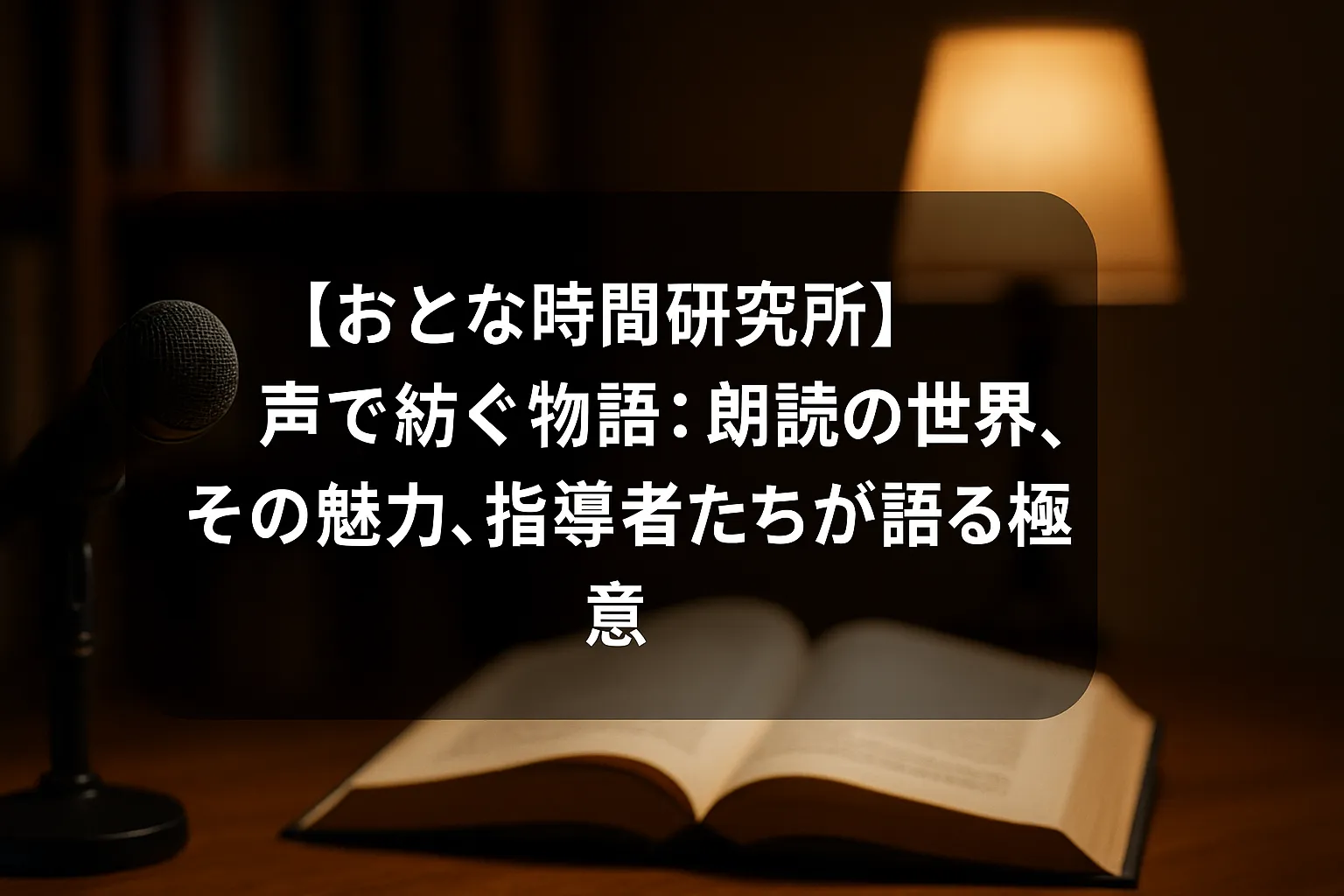



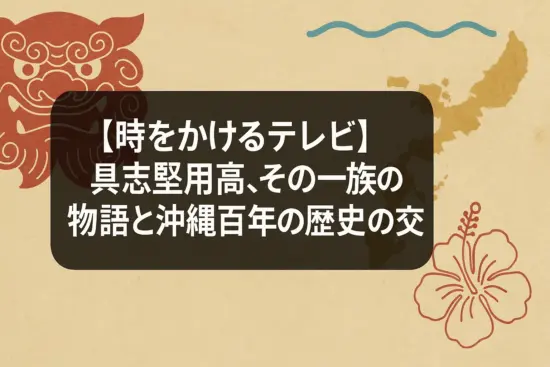
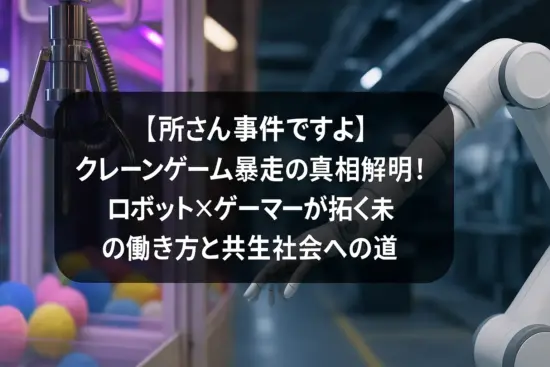

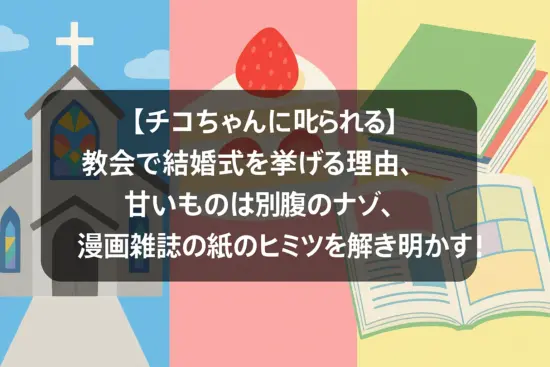

コメント