2025年4月23日にNHK『きょうの料理』で放送された特集「満喫!なにわの”食い味”」。
この中で紹介された「基本の昆布だし」は、多くの視聴者に衝撃を与えました。
この記事を読めば、なぜこの昆布だしが特別なのか、その秘密が分かります。
大阪料理の名手、上野修さんが伝授する、家庭でも再現可能な本格だしのレシピ、その驚くほどシンプルな材料、そして時間と手間をかけるからこそ得られる深い味わい。
大阪の食文化「食い味」の根幹をなす、この「基本の昆布だし」の全てを、初心者の方にも分かりやすく解説します。
今日からあなたも、だし名人を目指しませんか?
これぞ大阪の味!きょうの料理「基本の昆布だし」が衝撃的だった件
2025年4月23日放送のNHK『きょうの料理』、特集「満喫!なにわの”食い味”」をご覧になりましたか?
紹介された上野修シェフの「基本の昆布だし」は、まさに大阪料理の真髄。
そのシンプルさと奥深さに驚いた方も多いのではないでしょうか。
ここでは、なぜこのだしが「衝撃的」と言えるのか、その理由を紐解きながら、レシピの詳細を見ていきましょう。
大阪が誇る食文化の基礎が、この一杯に詰まっています。
【材料】たった2つ!絶品「基本の昆布だし」の秘密
驚くことに、プロが教える極上の昆布だしに必要な材料は、たったの2つだけです。
- 昆布: 45g
- 水: 1.2ℓ
この「昆布45gに対して水1.2ℓ」という比率(約3.75%濃度)がポイント。
だし素材の風味をしっかりと感じさせつつ、他の食材の味を邪魔しない、絶妙なバランスの旨味を引き出すための黄金比率なのです。
そして、使用する昆布にもこだわりがあります。
大阪料理では伝統的に、北海道の道南で採れる「真昆布」が珍重されてきました。
真昆布は肉厚で幅が広く、だしを取ると澄み切った見た目と、上品な甘み、そして濃厚で後を引くような旨味が特徴です。
このだしこそが、素材の持ち味を最大限に活かす「食い味」の土台となります。
昆布に含まれる旨味成分の代表格「グルタミン酸」を、この後の作り方で丁寧に引き出していきます。
感動の旨味!「基本の昆布だし」失敗しない作り方のコツは?
時間はかかりますが、手順は驚くほどシンプル。
しかし、その一つ一つに美味しさを最大限に引き出すための理由があります。
失敗しないためのポイントを押さえながら、丁寧な作り方を見ていきましょう。
- 1. 昆布を割る: まず、だしが効率よく出るように、昆布を手で適当な大きさ(数かけ)に割ります。ハサミを使っても良いでしょう。表面積を増やすことで、水に旨味が溶け出しやすくなります。
- 2. 一晩おく (水出し): 鍋に割った昆布と分量の水(1.2ℓ)を入れ、蓋やラップをして冷蔵庫で一晩(最低でも8時間程度)おきます。低温でじっくり時間をかけることで、昆布の主たる旨味成分であるグルタミン酸が、雑味なく水の中に溶け出してきます。
- 3. 加熱する (低温抽出): 翌日、昆布と水が入った鍋を弱火にかけます。ここが最大のポイント!**絶対に沸騰させないでください。** 鍋の表面が静かに揺らぐ程度、温度にして約60℃から80℃くらいを目安に、30分間じっくりと加熱します。沸騰させると、昆布の表面からアルギン酸などのぬめり成分や、えぐみが出てしまい、せっかくの澄んだ風味が損なわれてしまうのです。弱火でゆっくり温めることで、グルタミン酸以外の旨味成分も穏やかに引き出し、味に深みを与えます。
- 4. 昆布を取り出す: 弱火で30分加熱したら、すぐに火を止め、昆布を鍋から取り出します。これで、上品ながらもしっかりとした旨味を持つ「基本の昆布だし」の完成です。長く浸けすぎると、やはり雑味の原因になることがあります。
この「水出し」と「低温加熱」を組み合わせた二段階の抽出法は、昆布のポテンシャルを最大限に引き出すための、計算された技法です。
時間はかかりますが、速成のだしでは決して味わえない、クリアで洗練された、深い旨味が得られます。
完成しただしは、冷蔵庫で3日間保存可能です。
お吸い物や煮物、和え物など、様々な料理のベースとして活用できます。
まとめ:きょうの料理「基本の昆布だし」レシピのポイントについて
今回は、NHK『きょうの料理』で紹介された、上野修シェフによる「基本の昆布だし」のレシピとその背景についてご紹介しました。
材料は昆布と水だけというシンプルさながら、一晩かける水出しと、沸騰させない丁寧な加熱という工程に、美味しさの秘訣が詰まっています。
このだしこそが、素材の持ち味を活かす大阪料理「なにわの”食い味”」の基本。
ぜひご家庭で、この本格的な昆布だし作りに挑戦してみてください。
その違いにきっと驚くはずです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
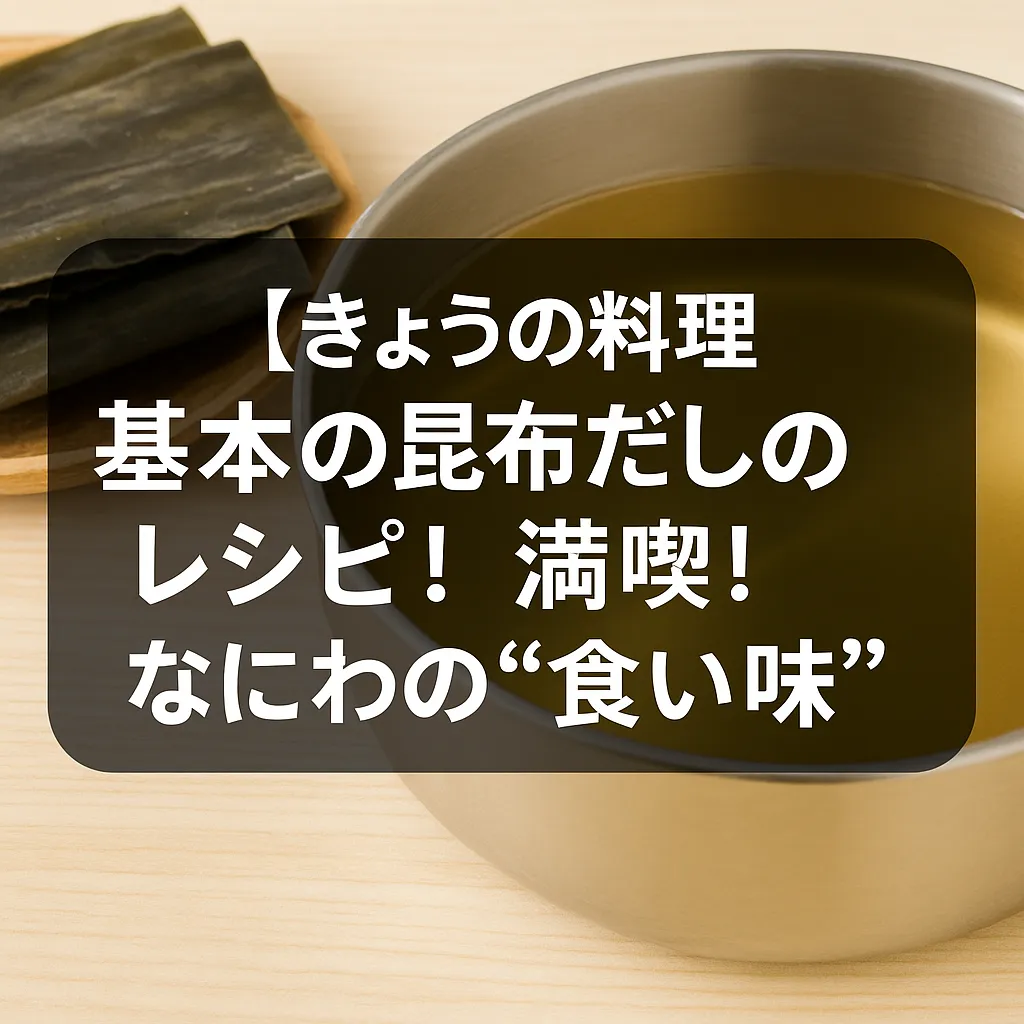








コメント