2025年5月18日に放送されたNHKスペシャル「日本企業の“勝機”とは?米中対立の裏にある成長戦略」では、激化する米中対立という未曾有の国際情勢の中で、日本企業が直面する課題と、そこからいかにして新たな成長の機会、すなわち「勝機」を見出そうとしているのかが多角的に報じられました。
この記事を読めば、番組で取り上げられた日本企業の具体的な戦略、例えばサプライチェーンの再構築、ASEAN諸国や欧州市場への新たな展開、日米間での電気自動車(EV)・再生可能エネルギー・人工知能(AI)といった先端技術協力の深化、そして国家戦略としての半導体産業の再興(ラピダスプロジェクトなど)の詳細が分かります。
さらに、投資コンサルタント齋藤ジン氏による経済分析や、これらの経済動向の背景にある社会構造の変化と日本が抱える課題についても理解を深めることができます。
NHKスペシャル 日本企業の勝機とは?米中対立下の成長戦略
この番組は、米中間の貿易摩擦や技術覇権競争、地政学的緊張が世界の経済秩序に大きな変動をもたらす中、日本企業がこの困難な挑戦に立ち向かい、それを乗り越えて新たな成長の機会を見つけ出そうとする姿を追ったものです。
米中対立、日本経済への衝撃と活路は?
米中両国の対立は、単なる二国間貿易摩擦を超え、世界の経済秩序やサプライチェーン、技術開発の方向性にも広範かつ深刻な影響を与えています。
日本経済および日本企業は、この地政学的変動の渦中にあり、その影響を強く受けています。
具体的には、米国による対中追加関税や中国の報復措置により、特に鉄鋼・アルミ製品、自動車部品、精密機械などの分野で輸出入コストが増大し、企業収益を圧迫しています。
ジェトロの調査では、在米日系企業の約4割が何らかのマイナス影響を認識し、調達先の変更を余儀なくされるケースが顕著です。
しかし、この危機的状況は、日本企業にとって新たな事業機会を創出し、競争優位性を再構築する好機ともなっています。
アメリカ市場で中国製品が後退した「市場の空白」を、日本の高品質な製品や信頼性の高い技術で埋める動きや、米中でも欧州でもない「信頼できる第三国」としての日本の立場を活かした国際的パートナーシップ構築の動きが見られます。
さらに、成長著しいASEAN諸国や欧州市場への積極展開、AI・EV・再生可能エネルギーといった成長分野での日米技術協力も活発化しています。
これは、日本が独自のポジションを戦略的に活用し、新たな国際分業体制の中で不可欠なプレイヤーとしての地位を確立しようとする試みです。
サプライチェーン再編!ASEAN・国内への大変革
米中対立と地政学リスクの高まりを受け、日本企業はグローバルサプライチェーンの脆弱性に対処するため、その再構築を喫緊の課題としています。
特に中国への一極集中リスクを回避する「チャイナ・プラスワン」戦略が加速し、ASEAN諸国が主要な受け皿として注目されています。
ジェトロの調査によれば、在米日系企業の4割が調達先の変更を検討または実施しており、主な変更先としてタイやベトナムが挙がっています。
例えば、東芝機械は射出成型機の生産拠点を中国から日本国内とタイへ、リコーは米国向け複合機の生産を中国からタイへ、京セラは米国向け複合機を中国からベトナムへ、シャープも米国向け車載用液晶ディスプレイの生産を中国計画からベトナムへと変更しています。
これは短期的なリスク回避だけでなく、ASEAN市場の成長性を見込んだ「攻め」の側面も持ち合わせています。
一方、経済安全保障や国内技術基盤の維持強化の観点から、一部生産機能の国内回帰(リショアリング)も進んでいます。
象徴的なのは、次世代半導体の国産化を目指す「Rapidus(ラピダス)」プロジェクトで、北海道千歳市に最先端工場を建設中です。
また、欧州市場では、高級歯ブラシブランド「MISOKA」が日本の微細加工技術を活かしフランスで成功するなど、高品質・高付加価値戦略が展開されています。
これらの動きは、調達先の多元化(マルチソーシング)、戦略的在庫積み増し、代替輸送ルート確保、国内拠点と海外拠点を組み合わせたハイブリッド体制の構築といった具体的な施策によって支えられています。
三菱電機やアイリスオーヤマなども、市場状況に応じた機動的な生産体制の再編やリスク分散を図っています。
日米技術協力の最前線!EV・再エネ・AIの未来
世界の産業構造を大きく変える可能性を秘めた電気自動車(EV)、再生可能エネルギー、人工知能(AI)の分野では、日米間の技術協力が深化し、未来産業の共創が進んでいます。
EV分野では、日本企業が持つバッテリー技術や高効率モーターなどの要素技術が強みです。
トヨタ自動車は、米国ノースカロライナ州に総投資額139億ドルを投じてEV用バッテリー工場「TBMNC」を建設中で、2025年4月からのバッテリー出荷開始を予定し、フル稼働時には5,100人の雇用創出が見込まれます。
さらにトヨタは日米合わせて最大7300億円を追加投資し、EV用バッテリーの年間生産能力を2026年にかけて最大40GWhまで引き上げる計画です。
ホンダも米国内のEV生産ハブに10億ドル規模の設備投資を実施。
日産自動車は、次世代の全固体電池開発で先進的な取り組みを見せ、2024年度中に横浜工場内にパイロット生産ラインを設置、2028年度の実用化を目指しています。
一方で、米国では公共充電インフラの整備遅れが課題です。
再生可能エネルギー分野では、水素エネルギーと洋上風力発電で日米協力が活発です。
豊田通商、トヨタ自動車、三井E&S、三菱重工などが米国内プロジェクトに関与。
特に三菱重工業は、ユタ州で大規模な水素混焼ガスタービン発電設備を受注し、2025年に水素混焼率30%での運転開始、将来的には2045年までに水素専焼を目指す画期的なプロジェクトを進めています。
日本国内でも、JERAとIHIが愛知県の碧南火力発電所で、大型商用石炭火力発電機で世界初となる燃料アンモニア20%混焼の大規模実証試験を2024年4月に開始しました。
AI技術はあらゆる産業に革命的変化をもたらすキーテクノロジーであり、日本政府もNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)を通じて「人と共に進化する次世代人工知能に関する技術開発事業」などを推進し、物流・運輸、介護・福祉、教育といった分野でのAI活用を支援しています。
アーサー・デイ・リトル・ジャパン、ソフトバンク、パナソニックコネクトは物流・小売分野で、内田洋行と京都大学は教育分野でそれぞれAI技術開発プロジェクトに取り組んでいます。
日米間のAI分野での大規模な共同開発はこれからですが、AIの倫理基準やガバナンス体制のルール形成で両国が連携する意義は大きいです。
半導体復権へ!国家戦略「ラピダス」の挑戦
かつて世界市場を席巻した日本の半導体産業は、経済安全保障上の最重要戦略物資としての価値が再認識され、国家戦略として「半導体産業の復権」が強力に推進されています。
その中核を成すのが、次世代先端半導体の国産化を目指す「Rapidus(ラピダス)株式会社」です。
ラピダスは、回路線幅2ナノメートル(nm)世代という世界最先端ロジック半導体の設計・製造技術確立を目指し、2020年代後半の量産開始を目標としています。
このため米IBM社から2nmノード技術を導入し、ベルギーの研究機関imecとも協力。
生産拠点は北海道千歳市に建設中です。
経済産業省は、2030年までに国内半導体関連企業の売上高を現在の約5兆円から3倍以上の15兆円超に拡大する目標を掲げ、IoT機器向けレガシー半導体強化、ラピダス等による次世代半導体技術確立、光電融合技術などの革新的技術実現という3ステップ戦略を推進しています。
日本の強みである高品質な半導体材料(シリコンウェーハ、フォトレジスト等)や精密な製造装置が、この戦略の重要な基盤です。
政府は、先端半導体の国内製造基盤整備のため、令和3年度補正予算で6,170億円、令和4年度補正予算で4,500億円を計上。
さらに経済安全保障推進法に基づき、半導体サプライチェーン強靭化支援事業に令和4年度補正予算で3,686億円を投じています。
台湾のTSMCによる熊本県への大規模工場誘致も政府支援の成果の一つで、地元大学との連携による人材育成や地域賃金上昇の兆しが見られます。
2022年5月には日米両政府間で「半導体協力基本原則」が合意され、国際連携も強化。
しかし、半導体技術は米中技術覇権争いの最前線であり、日本は難しい舵取りを迫られています。
持続的成長には人材育成も不可欠で、文部科学省は全国7大学を「半導体人材育成拠点」に選定。
JEITAの試算では、今後10年で国内主要半導体企業9社だけでも約4万3000人の専門人材が新たに必要とされています。
齋藤ジン氏が喝破!新自由主義の終焉と日本の好機
番組に登場した投資コンサルタントの齋藤ジン氏は、現在の米中関係を単なる貿易摩擦ではなく「冷戦状態」と捉え、偶発的衝突を含めた「戦争のリスク」を警告しています。
同氏は、1980年代以降の世界経済秩序を規定してきた市場原理主義、規制緩和、グローバル化といった「新自由主義(ネオリベラリズム)」が限界を露呈し崩壊しつつあり、経済運営の主導権が市場から政府へ移り、保護主義的なブロック経済化へ向かう「ゲームチェンジ」が起きていると分析します。
齋藤氏(オブザバトリー・グループ共同設立者、マネージング・ディレクター、ジョンズ・ホプキンス大学高等国際問題研究大学院(SAIS)修了。
著書に『世界秩序が変わるとき 新自由主義からのゲームチェンジ』)によれば、このゲームチェンジの主要プレイヤーは依然アメリカであり、そのアメリカが対中国戦略から次に経済的恩恵を与えようとする国が日本である可能性を指摘。
これは、冷戦期にアメリカがソ連封じ込めのために日本を経済支援した構図の再現とも言えます。
中国経済については、不動産バブル崩壊や2023年6月に過去最高の21.3%に達した若年層失業率などの国内不安定要因が、台湾問題など対外強硬策に向かわせるリスクも示唆しています。
このような世界的な構造転換の中で、日本は「数十年に一度のチャンス」を迎えていると齋藤氏は強調します。
その根拠は、アメリカの対中戦略転換に加え、日本国内で長年のデフレ経済下で企業内の余剰人員整理が進み、近年の人手不足と賃金上昇圧力が企業の生産性向上努力や構造改革を後押しする環境が整いつつある点です。
日本が新自由主義的グローバル化に過度に適応しなかったことが、結果として社会の安定を維持し、現在の転換期において強みになり得るとも述べています。
ただし、この好機を活かすためには、日本自身が大胆な国内改革を断行し、変化への適応能力を高める必要があると警鐘を鳴らしています。
成長戦略の裏側 社会構造の変化と未来への問い
日本企業の新たな成長戦略は、その背景にある日本社会の構造的な変化や課題と深く結びついています。
急速な少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少と深刻な労働力不足は、多くの産業で喫緊の経営課題です。
ラピダスやTSMCの工場新設は、地方の雇用創出や経済活性化に貢献する一方、高度専門人材の継続的な確保・育成や、工場の稼働に伴う水資源・電力供給・交通網といったインフラ整備の課題も生み出します。
齋藤ジン氏が指摘する中国の若年層失業率は日本にとっても対岸の火事ではなく、非正規雇用の拡大や産業構造変化に伴うスキルのミスマッチなどが若年層のキャリア形成に影響を与えています。
企業が追求する成長戦略は、こうした国内の社会課題解決にも貢献し、経済成長の果実が広く社会全体に行き渡る包摂的な成長モデルでなければなりません。
企業が短期的な利益追求だけでなく、CSV(共通価値の創造)の考え方に基づき、環境問題(GX)、地域社会貢献、従業員のウェルビーイング向上などに取り組むことが、持続可能な経済社会システム構築に不可欠です。
番組で紹介されたであろうラピダス関係者やサプライチェーン再編担当者たちの取り組みや信念には、企業家精神とイノベーションの萌芽が見られます。
また、先端技術の導入は、立地する地域社会との共存共栄が重要です。
TSMC熊本工場の事例では、経済効果への期待と同時に、地下水資源への影響や交通渋滞への懸念も指摘されています。
AIの介護分野活用においても、倫理的妥当性や人間的コミュニケーションへの影響など、技術開発段階から地域社会と共に解決策を模索する必要があります。
技術革新と地域社会の持続可能な発展が両立する新たな共生モデルの構築が求められています。
まとめ:米中対立下の日本企業の未来戦略について
NHKスペシャル「日本企業の“勝機”とは?米中対立の裏にある成長戦略」は、日本企業が直面する厳しい国際環境と、その中で見出される新たな成長の可能性を浮き彫りにしました。
サプライチェーンの再編、先端技術分野での日米協力、そして半導体産業の復権といった戦略は、日本経済の未来を左右する重要な取り組みです。
しかし、これらの「勝機」を確実なものとし、持続的な成長に繋げるためには、企業、政府、そして社会全体が一丸となって、構造改革や人材育成、イノベーション創出といった課題に真摯に取り組む必要があります。
最後まで読んでいただきありがとうございました。




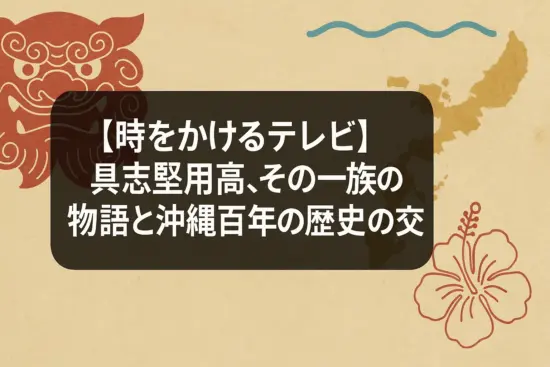
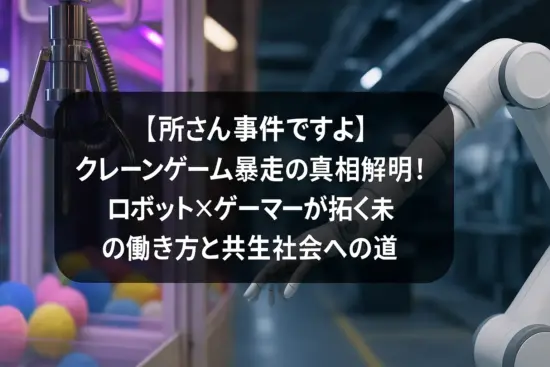

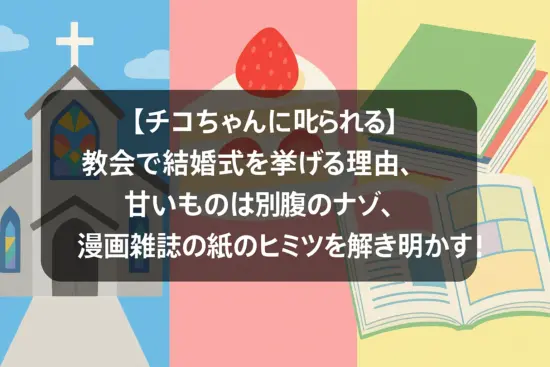

コメント